コミュニケーションから学ぶこと

日本コミュニケーショントレーナー協会のコミュニケーション講座が始まったのは東京校からでした。
今では、オンライン講座がメインとなりましたが多くの参加者と「コミュニケーション」というテーマで学びを深めてきました。
ところでこれをご覧になっているあなたは「コミュニケーションを楽しめてますか?」という問いに何とお答えするでしょうか?
もし「楽しめてない」という方がいらっしゃったら安心してください。
多くの方がコミュニケーションにストレスを感じています。
もしくは、ストレスを感じたことがある。とお答えするでしょう。
前提として「相手を喜ばせる」「相手の話に合わせる」「聞き上手になる」このようにコミュニケーションを成立させるには「相手を主人公」にしなければいけませんから、自分の気持ちよりも相手を優先した言葉や態度になりがちです。
コミュニケーションとは少し違いますが・・・もうすぐクリスマス、大切な人が喜ぶだろうと思ってプレゼントを渡します。
相手が喜んでくれなかったら残念に思いませんか?もしかしたら「せっかく気持ちを込めて買ったのに」と怒りがでてしまうかもしれません。
相手を喜ばせようと行動した際に予想外の反応をされたらストレスが掛かるんですよ。
それがどれだけ大切な人だろうと・・・
コミュニケーションってそういうもんなんです。
距離が近かったりすればするほど、気持ちが強くなればなるほどストレス反応がでるんです。
だから「コミュニケーションを楽しめる人」ってほとんどいないと思います。
もちろん上手く出来たり、成果が上がったコミュニケーションが取れた際はよろこんでください。
ストレス反応が起こるコミュニケーションの場合は、ストレスを避けるだけでなく学びに変えるプロセスも重要になります。
コミュ力をもし上げたいのなら、傾聴だけでなくストレスと向き合える「私」をトレーニングしてみると良いかもしれませんね。
静寂から学ぶ

物静かな空間から学ぶことがたくさんあります。
私一人しかいない空間で、静けさと仲良くなる。
私が存在している。という実感を強く感じるかもしれません。
安心を感じるかもしれませんし、寂しさを感じるかもしれません。
人によって感じ方は様々ですが、一人だからこそ気持ちや心と向き合い、「私」を知ることができ、何かに迷ったときは、静かな空間で私と向き合うことで「大切な何か」を教えてくれる気がします。
私と向き合う学習は【コミュニケーション心理学】で体験することができます。
私が主人公の心理学。誰かとではなく、私の時間。と人生。のヒントをみつけてみませんか?
TOP1%メンター養成コースとは?──言葉と“古の叡知”で人を支えるメンターへ
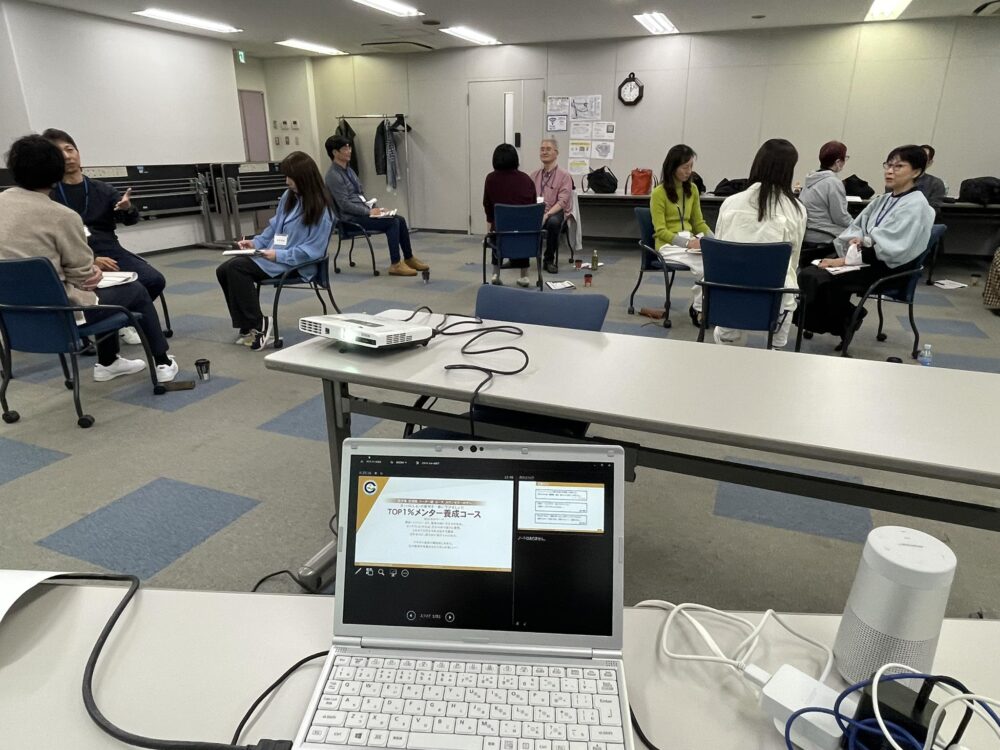
先日、「TOP1%メンター養成コース」が開催されました。
単なる“技術”や“コミュニケーションのテクニック”ではありません。
- 講座では、歴史上の思想家や宗教者、文人たちの言葉──たとえば ピーター・F.ドラッカー、 池田晶子、 道元禅師 などの“古の叡知”から引用される言葉の力と、その背後にある「意味」の深さに光をあてました。
- そうした言葉は、単純な会話以上の“影響力”を持ち、「受け手の人格、価値観、信条、などを根こそぎ変える」力を秘めているとされます。
今回の「講座は「言葉を道具やテクニックとして使う」のではなく、「言葉の魂、言葉の重み」を理解し、それを相手の変容の力に変える“在り方”を学ぶ場です。
毎年テーマが変わる講座。
言葉には、人の心を動かし、時には人生を変える力があります。
その力を磨き、誰かの未来を支えるメンターとして、来年もお会いできるのを楽しみにしています。
簡単なテストでは自分はわからない理由|心理学でわかる“本当の自己理解”の深め方

なぜ簡単なテストでは自分はわからないのか?【心理学的な理由】
性格は固定ではなく“状況で変化する”
心理学では、性格は環境・相手・役割の影響を強く受けるとされています。
- 仕事では落ち着く
- 家族の前では安心してよく話す
- 人が多い場所では疲れやすい
こうした違いは矛盾ではなく、人として自然な反応です。
短いテストは「複雑さ」を拾えない
信頼性のある心理検査は数十〜数百問。
数問の簡易テストが当たらないのは当然です。
気分や体調で結果が変わる
その時の感情状態(不安・疲労・緊張)が答え方を左右します。
“理想の自分”で答えてしまう
人は無意識に「こうありたい自分」を選びがちであり、本質ではなく“願望”が反映されることもあります。
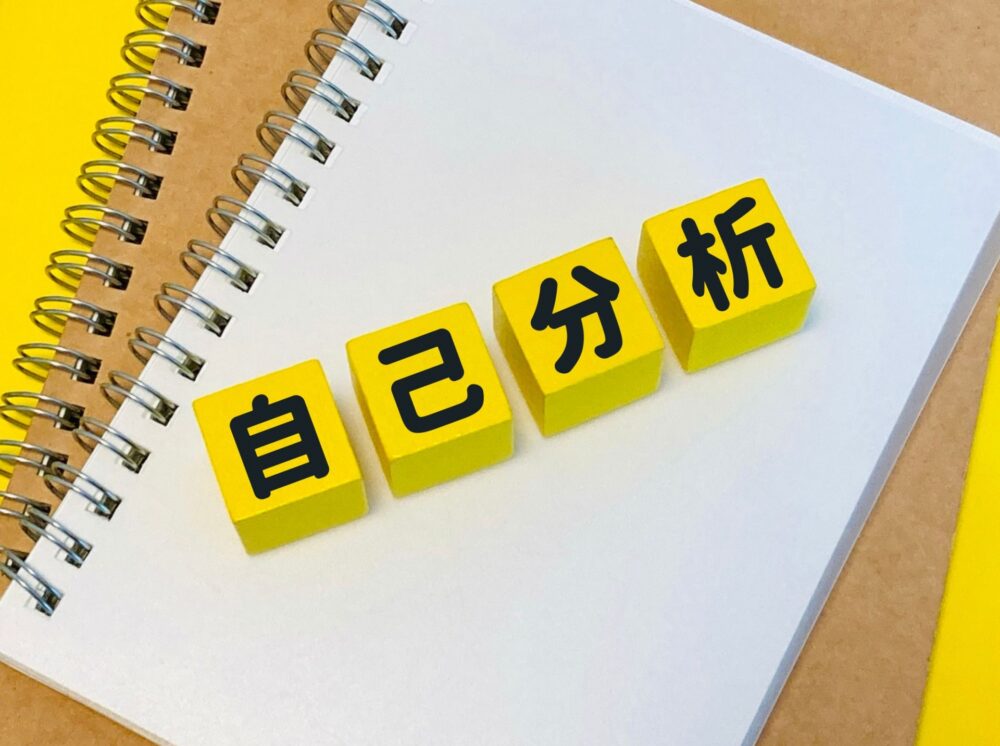
自分が「わからない」と感じるのは悪いことではない
心理学者たちは、自己理解を“生涯を通して深まっていくプロセス”と捉えています。
短いテストで本質がわからないのはむしろ当然で、「自分はこんなに複雑なんだ」と理解できている証拠でもあります。

本当の自己理解が深まると起きる変化
● 選択に迷わなくなる
自分の軸がわかることで、判断がスムーズになります。
● 他人の意見に振り回されなくなる
「自分の基準」が育つので、必要以上に比較しなくなります。
● 関係性のストレスが減る
どういう人や環境で疲れやすいかが分かるため、調整しやすくなります。

心理学が推奨する“本当の自己理解”の方法
● 行動を記録し、パターンを見る
「どんな時に疲れたか/楽しかったか」を書くと本質的な傾向が見えます。
● 他者フィードバックを取り入れる
心理学の“ジョハリの窓”が示すように、人は自分の盲点を他者の視点で知ることができます。
● 長期的に振り返る
日ごとの気分ではなく、半年〜一年単位で自分の傾向を分析することが大切です。
● 対話による探索(カウンセリング・コーチング)
専門家との対話は、自己理解の確度を高める方法として有効。
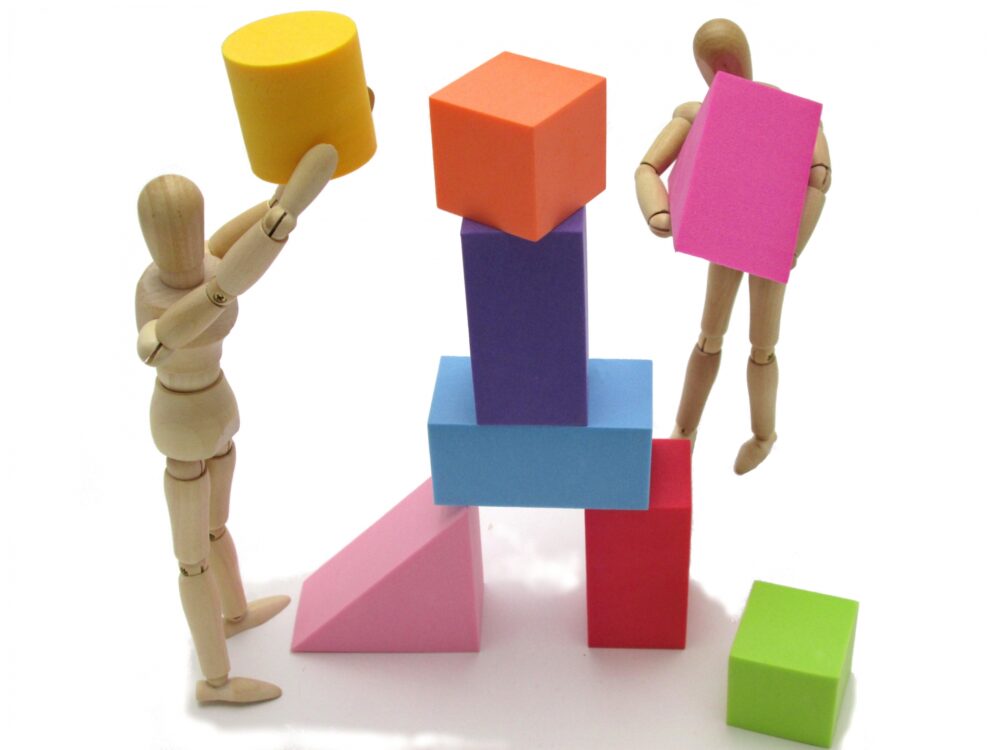
簡単なテストは“入口”として使うのが正解
短い診断は「なんとなく方向性を知る」ためのツールです。
地図アプリで現在地をざっくり確認するようなもの。
本当の自己理解は、日常の行動・人間関係・価値観を積み重ねていくことで深まります。
まとめ:自分は簡単なテストではわからない。だからこそ面白い
人はシンプルな存在ではありません。
経験や環境に応じて変化し続けるため、短時間のテストでわかるはずがない。
その“わからなさ”こそが、あなたの複雑さ・豊かさ・魅力でもあります。
心理学の視点を取り入れながら、時間をかけて「本当の自分」を見つけていきましょう。
プライバシーと心のバランスを取り戻すために

「見られている感覚」が心に与える負担

誰かの視線を常に意識しながら生きると、人は自然と“良い自分”を演じようとします。
それは社会生活では必要なスキルでもありますが、長く続くと心が休まりません。
心理学的には、こうした状態を「持続的な自己モニタリング」と呼び、ストレスや自己否定感の原因になりやすいと指摘されています。
つまり、いつも“誰かの目”を気にする社会では、「自分らしくいる」ことがどんどん難しくなるのです。
「さらけ出すこと」が善になってしまった社会

現代では、「オープンであること」「正直に話すこと」が称賛されます。
もちろん、それ自体は悪いことではありません。
ですが、過度に求められると、「隠す=悪」「秘密=不誠実」という偏った価値観が生まれてしまいます。
本来、秘密は人を守るための心の壁です。
全てを共有しないことは、他人を拒絶する行為ではなく、自分の輪郭を保つための自然な防衛反応なのです。
「秘密を持つ自由」を意識的に取り戻す

今の時代に完全なプライバシーを保つのは難しい。
でも、心のプライバシーつまり「何を話すか」「何を話さないか」を選ぶ自由は、まだ自分の手の中にあります。
たとえばこんな小さな行動からでもいいんです。
- SNSで「書かないこと」を決めておく
- 夜はスマホを置いて自分の時間を持つ
- 誰にも言わない“自分だけの楽しみ”をつくる
秘密は孤立ではなく、「自分を整えるための静かな時間」なのです。
「見せない勇気」が心を守る

情報があふれる世界では、何も隠さずに生きることが理想のように見えます。
でも、本当に大切なのは「見せない勇気」ではないでしょうか。
心の奥に、誰にも触れられない小さな空間を持つこと。
そこにこそ、人間らしい自由と安らぎが宿ります。
秘密は恥ずかしいものではありません。
それは、あなた自身を守るための優しい盾なのです。
残席1となりました!TOP1%メンター養成講座

TOP1%メンター養成講座
2025年11月29日・30日(土日)に開催します。
残席1となりました!
満席になってしまった場合は、お申し込みができなくなります。
ご容赦ください。
毎年、大人気のこちらの講座ですが今回はいつもと違う?
新しい(深化した)TOP1%メンター養成講座をお届けすることができます。
はじめての方も参加可能ですが、当協会の講座(1日講座以上)を受講していただいていると、学びがさらに深まるでしょう。
刺激と学び溢れる強烈な2日間になること間違いなさそうです。
メンタリングとは?
はじめての方は、ぜひご覧ください。
より詳しい説明はコチラ
「許す」という技術の条件

謝られたら許せますか?
「謝った相手を素直に許すことができないんです。」こんな相談を受けたことがあります。
皆さんはいかがでしょうか?素直に許せますか?
そもそも素直に許す。とは一体どういうことなのか。
コミュニケーションにおいて「許す」という技術は、高度で難しいものなのです。
相手を許す。自分を許す。それらを含めても中々すっきりしないことの方が多いかもしれません。
NGな許し方

ありがちなコミュニケーションで「条件付け」があります。
「〇〇したら許してあげる」「××しないと許してあげない」このように条件を付けるというのはおススメしません。
もちろんエンタメとして、双方が納得しているのであれば問題ないでしょう。
TVなんかで「〇〇できれば△△」なんて企画はたくさんありますから。
ただし、お互いがストレスのかかる条件を付けて、コミュニケーションをしようとしても人間関係は良好になりません。
それどころか、間違いなく悪化するでしょう。
中には自分だけを鬱憤を晴らすために過度な謝罪を要求する大人もいます。
そういった人とは付き合わないのが一番だと思いますが・・・(苦笑)
条件を付けの「許す」は、成熟した大人ならきっとしないでしょう。
モヤモヤするのは?

許してからモヤモヤしてしまう方。
安心してください。(笑)
意外と普通かもしれません。
自分が不快になることをされたとして、ストレスが掛かるのは当たり前のことです。
許しても、許さなくても、きっとモヤモヤするんです。
そんな中、あなたは「許す」という選択をしたのです。
条件付けではなく、「無条件に相手の謝罪を許した」これが大切です。
今後、対象の人とお付き合いをしていくかは別として、、、許すということをしたんです。
傷つけられたから

そうは言っても中々許せないのは当たり前です。
それは、「あなたが大切にしていた体験や学び(尊厳)を傷つけられたから。」それが大きければ大きいほど、相手が謝罪をしても中々許すのが難しいでしょう。
すぐに相手を許さなくてもいいですし、これからも許せないかもしれません。
いつか許す日が来るかもしれませんし、思い出さない方が楽なら、それもよい選択なのでしょう。
そんな中で、「私が悪いから傷つけられたんだ。」
「あの時、私が○○していればこうはならなかったんだ。」このような自分に対する怒りや悲しみに関しては、許してあげてください。もちろん、無条件で。
自分で自分に「ごめんなさい」は、人に伝えるより難しい。
だからこそ、自分に対する「許し」は、人の謝罪を許容するより難しい。
それができると、心はスッと軽くなります。
冒頭の質問「素直に許せない」これは、傷が大きければ当たり前です。
そして「許す」ということを学んでないのかもしれませんし、誤った許し方を使っていたのかもしれません。
そう思った人は、少しずつ慣れていけばいいんです。
家族、友人、職場、そして・・・自分自身
人間関係において毅然と「許す」ことができる人って、魅力的ですよね。
受容と問いかけ

受容と問いかけ
カウンセリングやコーチングをする上で土台になる信頼関係の構築のスキルが
受容+問いかけです。
気持ちは、わからない?
しかし、ここで使われている受容は「あなたの気持ちわかる」「きっとこうだったのね。」など受け入れるような言葉ではありません。
なぜならば、受け入れるというのは、多くの場合、無理があるのです。
それは、人それぞれ体験が違うから。
同じような体験をしても、その時に感じていた感情や表情、考え方、行動は、人それぞれ違うからです。
だから、安易に「あなたの気持ちわかります」などと言ってしまうと、信頼関係が損なわれる危険性があります。
自分ではなくて相手
自分が「わかります。」ではなく相手から「わかってもらえた!」と言う状態を作るスキルが受容です。
受容のスキルとしては1つが「オウム返し」と言うスキル。
これは、相手の言ったことを伝え返すスキルです。
「今日は電車できました。」「今日は電車なのですね。」
こんなやりとりがオウム返しになります。
上手に使うには?
オウム返しのポイントは・・・?
出来るだけネガティブなワードは返さないことです。
例えば「彼に振られちゃった」「振られちゃったんだね」
この様な会話だと、余計落ち込んでしまう方がいらっしゃいます。
オウム返しは出来るだけマイナスな言葉にならないようにすると良いと思います。
「彼に振られちゃった」→「そんな事があったんだね」など,工夫をしながらコミュニケーションをしてみてください。
ねぎらい
受容のもうひとつのスキルがプロセスリフレーミングです。
日本で言うとねぎらいと言うスキルになります。
先ほどのオウム返しは、相手の言葉とコミュニケーションをする。
プロセスリフレーミングは、背景にコミュニケーションをします。
例えば、子供が「ママ・・・テストの点が悪かったんだ。」と落ち込んで、見せてきたとします。
子供の背景は、
「見せたら怒られるかな。」
「お母さん、残念な顔するかな」
「見せたくないな」こんな気持ちがあるのだと思います。
そして、言葉に出ていない気持ちを感じ取りコミュニケーションをすると・・・
「言いづらかったね。」「正直に言ってくれたから嬉しいよ。」
この様な言葉がプロセスリフレーミングといいます。
相手を安心させる言葉が受容です。
こういった言葉がかけられると「わかってもらえた」という気持ちが出て本音で向き合うことができます。
カウンセリングやコーチングでもクライアントが「わかってくれた!」と思うまで問いかけをしても本音での会話は難しいでしょう。
大切なのはしっかりとした受容を使い信頼関係を構築することです。
コミュニケーション 褒め方

こんにちは
トレーナー協会の猪瀬です。
褒め方
今日は、「上手な褒め方」について、お話させていただきます。
コミュニケーションにおいて、ネガティブな言葉の伝え方に悩む人は多くいらっしゃると思います。
では、ポジティブな言葉「褒め言葉」を、どのように伝えるかについては、どうでしょうか?
受け取りにくい褒め方
例えば、Aさんに「素敵ですね!」と伝えたとします。
そのような場面で「いいえ、とんでもないです…」と謙遜されてしまったことはありませんか?
実は「Aさん、素敵ですね」という言葉は、相手を評価するコミュニケーションであり、そのようなコミュニケーションは、「受け入れる」、「受け入れない」の判断を相手に委ねた状態になってしまっています。
そのため「謙遜」や「遠慮」といった文化のある日本人は、褒め言葉を素直に受け取ることができず、「NO」と言ってしまいがちです。
せっかく素敵な言葉を伝えようとしているのに、何だか、もったいないですよね。
自分の気持ちを伝える
そんなときは、少し工夫をしてみてください。
「Aさんを見ていると元気になります」
「Aさんと話していると優しい気持ちになれます」などの言葉で自分の気持ちを伝えてみましょう。
すると、相手も気持ちよく「褒め言葉」として受け取ってくれるようになります。
決めつけはしない
怒っている人に「怒っているよね?」と聞くと「怒ってないよ!」と言われることも多いように(笑)
相手を評価する(決めつけてしまう)伝え方は多くの場面で、あまり良いコミュニケーションとはいえません。
上手な褒め方とは、「相手の評価を伝える」のではなく、「自分の気持ちを伝える」ことを意識することが大切です。
コミュ力。ってなんだろう?

コミュ力とは?って考えたことありますか?
Wikipediaで調べてみると・・・「他者と意思疎通を上手に図る能力」を意味する。と
書いてあります。
話し上手・聞き上手という訳ではなさそうな気がしませんか?
その場に応じて、場に合わせた対応が出来ることが重要になりそうです。
言ってしまえば「演技」をすることです。
私たちがお伝えしているのは「コミュニケーションの主人公は受け手」であり
「自分」ではないということです。
正直でいることは、悪い事ではありません。むしろ良いことでしょう。
しかし、正直で居ると周りと上手く関われない場合もあります。
行きたくない飲み会に参加して、「私、こんなところに来たくありません。」と
正直に伝えたら場が凍ってしまうわけです。(一部受容してくれる方もいます。)
素直に気持ちを伝えたり、言われたりするのが苦手な方が
日本人に多いのも影響があるかもしれません。
もちろん、気持ちをストレートに伝えることは悪い事ではありません。
しかし、それはコミュ力ではなく、自分の気持ちを言っているだけに過ぎないのです。
「相手に合わせる」これがコミュ力を上げるコツです。
好きな人が「遊園地に行きたい」と言ったら、遊園地は苦手だけど合わせてみる
この様に自分が好意を持っている相手に対しては、合わせるのがそこまで苦ではないのに
苦手な人に合わせるのは苦痛というのは「自分のテーマ」になります。
苦手なお客様・上司と関わるときでも、コミュ力が高い方は「上手く合わせる」ことが
出来ているはずです。
言葉が必要なら話をして、聞く必要があれば話をせずに聞くことができる。
だからこそ、言い方が悪いと思われてしまうかもしれませんが
「演じる」ことが関係を構築するうえで重要なテーマになります。
自分の気持ちはどうなりますか?
確かに、自分の気持ちも大切ですね。
しかし、それはコミュ力のテーマではなくて「心理」のテーマですから
コミュニケーションを学んでも解決しないことがほとんどです。

コミュ力で心の問題は解決しません
「イライラ」「モヤモヤ」は、コミュニケーションを学んでも対応できません。
生きていれば苦手な人と出会い、予期しない失敗が起こり得るからです。
「相手を怒らせないようにしたい。だから、我慢している。」そんなテーマがあって場合
相手を怒らせないようにする。を優先的にしたいなら、「コミュニケーション」を学ぶ。
我慢している自分をどうにかしたい。を優先するなら「心理」を学ぶ。
このように学びたいことを分けて体験していった方が良いでしょう。
逆を言ってしまえば、「心理」を学んでもコミュ力は向上しにくいのです。
自分が、学びたいことを明確にして、ご自身に合う学習をしましょう。
講座選びに困ったら「無料面談」をご利用ください。


最近のコメント