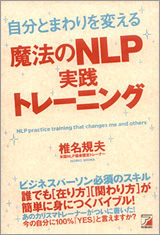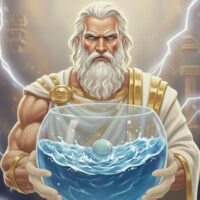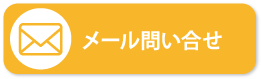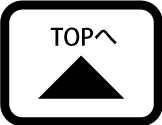ACTは、脳科学・認知科学を超えている――形而下から形而上への橋としての行動理論
投稿日:2025年10月16日 / 最終更新日:2025年9月4日

「心の問題は、脳の問題ではない」
そう聞いて、どう感じますか?
研究者たちが自ら気づき始めた脳科学の限界。
そして、最新の心理学で注目を集めるACTは、私たちが本当に大切にしたい価値へと行動を向けるアプローチで、生きる道を示してくれます。
その可能性の広がりは、セラピーの一つの手法だったACTが「アクセプタンス&コミットメント・セラピー」から、「アクセプタンス&コミットメント・トレーニング」へと呼称が変化したことからも証明されているのかもしれません。
目次 [閉じる]
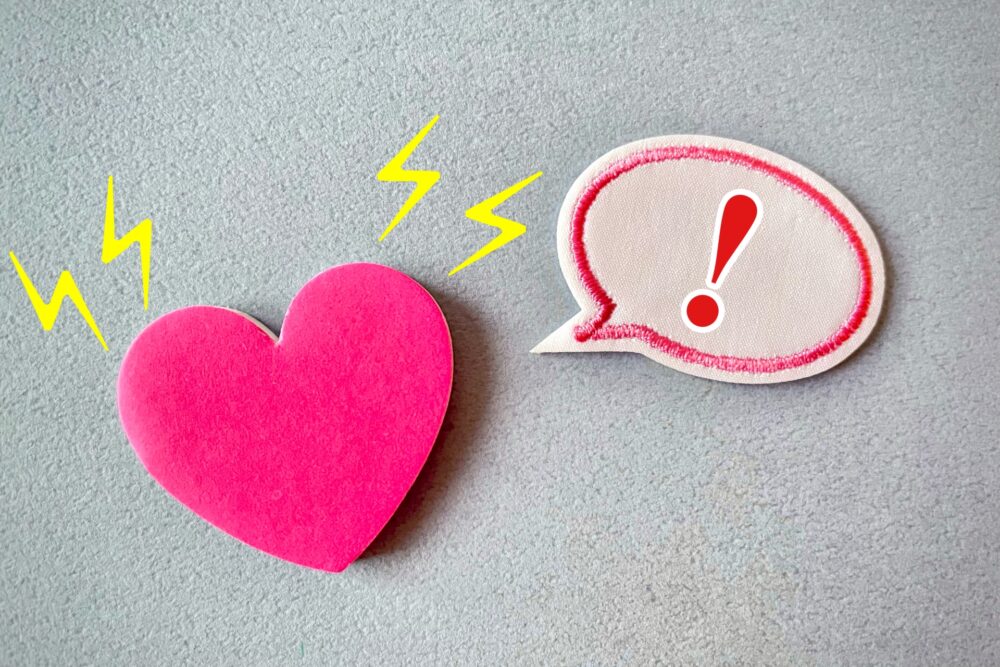
ACTとは何か ――注目は「苦しみ」を排除しない心理療法
脳科学で心理を探求する限界
私たちはいつの間にか、心の苦しみを「脳のエラー」や「思考の歪み」として捉えることに慣れてしまっています。しかし、私たちの心の痛みは、本当に「脳の誤作動」なのでしょうか?
人間の苦悩は、脳内化学物質のバランスだけで本当に解明できるのでしょうか。
脳科学は万能なのでしょうか?
ストレス、不安、自己否定、喪失、孤独といった感情は、脳内のエラーやホルモンバランスだけで説明し尽くせるものではないかもしれません。脳科学者たちの一部は、平然とその限界を語り出しています。
ACTは脳科学を否定するものではありません。ただ、脳科学だけではいつまで経っても解消しない心の領域があることを静かに教えてくれているのです。
脳科学の限界。「悩む」は「苦悩」になる。
次に、心の問題は、悩むことで解消できることなのでしょうか。
一度立ち止まって考えてみましょう。自分の常識を疑ってみましょう。
これは真実です。心の問題は悩んでも解消できません。
私たちは、心の問題を解消した方たちに、「悩みをどうやって解消しましたか」と同じ質問を、20年間、してきました。
答えのベストスリーです。
- 忘れる
- 寝る
- 飲む、食べる、ジムに行く
これらで問題は気にならなくなるでしょう。しかし、問題が解消されたとは言えません。このように「悩む」ことでは、問題は先送りになるばかりで、解消されることがないのが現実です。
ACTは「悩む」をしない。
ACTは1990年代に、アメリカの臨床心理学者スティーブン・C・ヘイズによって提唱されました。彼はネバダ大学リノ校心理学部の名誉教授。関係フレーム理論(RFT)の提唱者として知られ、それを基盤とした心理療法ACTを考案しました。
きっかけは、ヘイズ自身が経験したパニック障害でした。従来の認知行動療法で“治そう”としたが、思考を修正しようとすればするほど、症状が悪化してしまいました。
やがて彼は、「思考と戦うこと」そのものが、さらなる苦しみを生むことに気づいたのです。要するに解消しない問題を「悩む」ことで、その問題が「苦悩」に発展してしまうということです。これは大切なことです。
そこから彼は方向転換します。「思考や感情は消せない。ならば、それらとどう関係を築くか。」
これが、ACTの核心だ。ACTでは、思考や感情を否定しません。
負の感情、負の思考を変えることも、抑えることもしないのです。「悩む」ことをしないのです。
ただ、「そこにある」と認め、「そのままにして」、そこから自分の価値に基づいた行動を選ぶようにします。
この態度は、もはや単なる心理療法という技術を超え、まさに「生き方」と呼べるものです。
形而下から形而上へ ―― ACTが拓く道

行動療法の一つとして誕生したACT。その療法は単なる「刺激と反応」ではありません。むしろ、「意味に向かう行動」です。ここに、形而下(感覚・行動・体験)から形而上(価値・意味・存在)への道が拓かれます。
人は、「人が、なぜ生きるのか?」という問いには、簡単には答えられません。
しかし、「何を大切にして生きるのか?」という問いには、時間をかけずに見つけることができるものです。
ACTはこの問いを、「価値(values)」という概念で導いてくれます。
価値は、正解を求めることではなく、生きることの軸であり、選び取る方向であり、「いま・ここ」における決断の指針のことです。
その指針は、どこから響いてくるのか。
それを日本の古い文化では、天の声を聞くと伝えられたりしています。
仏教では、発心することで仏心に囲まれるということに似ています。
それは、個人の思考にとらわれず、感情に押し流されず、“価値に向かって歩み続ける”という行為が、人間の存在を形づくっていき、形而下であるはずの行動が、やがて自己の深部を照らし、形而上の問いに静かに触れていくプロセスです。
ACTと禅、哲学の交差点。

ACTと禅との接点。
「今、ここに坐る」
「無心である」
「手放す」
ACTの「マインドフルネス」や「アクセプタンス(受容)」は、禅的実践と深く通じ合っています。「今、ここに坐る」「無心である」「手放す」。禅そのものです。
たとえば、あるがままの思考や感情に気づき、それらを変えようとせず、ただ共にあるという状態をつくります。それは、仏教的な「空(くう)」という何ものでもない混沌を、秩序に変えていく道程です。
ヘーゲルとの響き合い
ヘーゲルの「止揚」は、矛盾を否定せず、内包し、より高い意味へと統合する運動でした。
それはまさに、ACTです。「不安や葛藤を避けずに新たな価値を発見し、それを軸にして行動する」。そのプロセスは、止揚そのものです。
西田幾多郎との響き合い
また西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」とも似ています。矛盾する葛藤を統合していくプロセスは、それであり、ヘーゲルの止揚そのものです。
ACTは“科学”であり、“哲学”

ACTは、日本で唯一の心理の国家資格「公認心理師」試験にも頻出するほど、心理学の領域で確固たる地位を築いています。
ヘーゲルの止揚や西田幾多郎の絶対矛盾的自己同一の概念に似たACTのプロセスは、哲学そのものでもあります。ただしそれは、言葉で語る哲学ではなく、選び、歩み、悩み、折れ、立ち上がる哲学であるということ。
ACTは、今を生きる私たちにとって、最も静かで、最も力強い「問いのかたち」なのかもしれません。
ACTの神髄を、開発者が語ります。
「心理的柔軟性があれば、すべてACTだ」
心理的柔軟性とは、知っていることなど何もなく「無知の知」の生き方のこと。「無知の知」で生きるとは、自分自身で「本当」を問い、その瞬間瞬間を丁寧に生きることです。
日々新たに生きる人間の「無知の知」世界に、科学が入り込むなんて不可能ではないでしょうか。
ACTは、心理療法の枠を超えました。今では、医療、福祉、教育、産業など、それぞれの分野を超えて注目されています。
だから、「アクセプタンス&コミットメント・トレーニング」と言われるようになったのです。