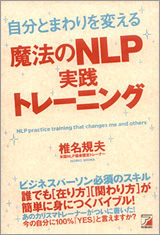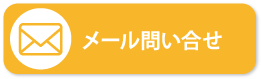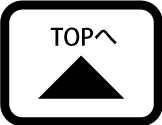【解説】コミュニケーションで失敗する人に共通する7つの特徴!|コミュニケーションで成功するためのコツ
投稿日:2025年8月4日 / 最終更新日:2025年8月12日

AIが正しいのか?
コミュニケーション専門スクールとして長年実績のある私たちの見解が正しいのか?
AIは、世間一般の常識。
私たちは、創業からコミュニケーションのトレーニングを20年続けてきた実績。
どちらが正しいのでしょうか?
「正しい知識」を実践しなければ、成果は出ないでしょう。
この記事では、AIが記した「コミュニケーションで成功するコツ」をもとに、世間で常識とされているコミュニケーションについて、コミュニケーション専門校の先駆者として長年コミュニケーションをお伝えしてきた私どもの考えを交えて解説します。
さらに、なぜコミュニケーションがうまくいかないのか、コミュニケーションで失敗する人に共通する7つの特徴をお伝えします。
人間関係、やる気、自己実現に、きっと役立つでしょう。
皆様の日常に置き換えて読んでいただけると嬉しいです。
目次 [閉じる]
- 1 AIが記したコミュニケーションで成功するコツは「正しい知識」?
- 2 【コミュニケーションで失敗する人の特徴①】自分の意思から伝えようとする
- 3 【コミュニケーションで失敗する人の特徴②】言葉だけでコミュニケーションをしようとする
- 4 【コミュニケーションで失敗する人の特徴③】感情的、衝動的にコミュニケーションしてしまう
- 5 【コミュニケーションで失敗する人の特徴④】異文化のテクニックを使ってしまう
- 6 【コミュニケーションで失敗する人の特徴⑤】意見の違いを尊重しない
- 7 【コミュニケーションで失敗する人の特徴⑥】上から目線のコミュニケーションに気づけない
- 8 【コミュニケーションで失敗する人の特徴⑦】相手を変えようとしてしまう
- 9 指示や命令などの言語情報は、コミュニケーションを成立させる一つの要素に過ぎない
- 10 相手は自分の期待するものを知覚(見たい、聞きたい、感じたい)したい
- 11 まとめ|コミュニケーションで成功するためのコツとは
AIが記したコミュニケーションで成功するコツは「正しい知識」?

AIに「コミュニケーションで成功するコツ」を尋ねたところ、7つのポイントが記されました。
AIが記した文章に、日本で一番初めにコミュニケーションの専門スクールを開設した私たち考えを併記します。
<コミュニケーションで成功するコツ>
AIが提示した情報 | 私たちの考え |
1.相手を理解し、共感する姿勢を持つ。 | その通りです。 |
2.明確で具体的に伝える。 | これは時と場合によります。仕事の指示を明確で具体的に伝えたら、それを実践する者はやる気が起きるのでしょうか? また、プライベートでは、起きた出来事を明確には言えなくて、抽象的になることが多いですよね。 |
3.フィードバックを受け入れる。 | その通りです。社会的フィードバックは、自分とまわりを理解するリソースです。 |
4.非言語コミュニケーションを活用する | その通りです。コミュニケーションとは、非言語のやり取りです。 |
5.自己表現と相手の尊重のバランスを取る。 | 違います。相手の意思を確認してから、私たちは自分の意思を伝えるチャンスに恵まれます。 |
6.誤解や曖昧さを避ける。 | 少し違います。日本文化では曖昧さが重要です。 高い専門性、能力を持つメンバーには、方向性を曖昧に伝えるだけの方が成果につながる場合も多いです。 |
7.感情をコントロールする。 | まったくの的外れです!感情はコントロールできません。 |
AIが記したのは、世間一般の常識です。
今回の目的は、AIと争うことではありません。
しかし、その「常識」が間違いだとしたらどうでしょう?
だって、コミュニケーションのテーマって、長い間、進歩がないですよね。
次の章からは、コミュニケーションで失敗する人に共通する7つの特徴をご紹介します。
【コミュニケーションで失敗する人の特徴①】自分の意思から伝えようとする

AIによると「コミュニケーション」とは、「情報、感情、意見などを相互に伝達し、理解し合うプロセス」です。
単に言葉を交わすだけではなく、非言語的な要素(表情、ジェスチャー、態度)や文脈、相手の立場を理解し、共感することが含まれます。
コミュニケーションの目的は、誤解を避け、相手との理解を深め、より良い関係を築くことです。
AIの視点では、コミュニケーションは常に相互作用とフィードバックのプロセスであり、単なる「伝える」行為ではなく、相手と理解し合うための双方向の協力と捉えられます。
AIが示すようにコミュニケーションは「双方向の意思の疎通」ですが、送り手と受け手がいる場合、送り手から先に意思を伝えると、コミュニケーションはほぼ失敗します。
失敗例を二つご紹介します。
まずは、部下に経理から営業職への配置転換をお願いしたい上司とその部下との会話です。
上司:「経理部から営業部に代わってもらうことになりました」
部下:「嫌です」※口下手で営業が向いていないと自覚していても、本音は言いづらいものです。
すると、こんな感じでしょうか?
上司:「経理部から営業部に代わってもらうことになりました」
部下:「営業ですか…。口下手なのはご存じですよね」
上司:「だからこそ、協力してほしいんだ…」
部下:「経理志望で入社したので、このままでお願いします」
上司と部下は、双方に不快な感覚が残りますよね。
もう一つ。例えば、新入社員歓迎会を開催したい先輩社員と行きたくない新人との会話です。
先輩:「歓迎会開催するから、来てね!」
部下:「私は、そういうの大丈夫です」※今の子なら言いそう。40年前に会社員になった私も言うかも!
どちらのケースとも、受け手である相手の意思を確認する前に、送り手側の意思から伝えてしまっています。
コミュニケーションの目的は、双方向の意思の疎通です。
相手の意思を確認してから、自分の意思を伝えることが大切です。
そして場合によって、相手の意思を確認した後には、自分の意思を伝える必要がなくなるかもしれません。
【コミュニケーションで失敗する人の特徴②】言葉だけでコミュニケーションをしようとする

「言葉」は単なる情報にしかすぎません。
例えば、「私は総理大臣です」と言われても、信じないですよね。
「私は日本語を知りません」…これも信じないですよね。
「私は正直者です」「私は31歳です」「私はプロサーファーです」「私は趣味でチョコレートづくりをしています」「私はタワーマンションの最上階に住んでいます」…どれかは信じていただけますか?
これらの言葉のうち、一つだけが本当です。どれが本当なのか分かりますか?
多分、分からないですよね。
なぜ、分からないのか。それは、「非言語情報」がまったくないからです。
このように言葉だけでは、意志を伝えることは難しいのです。言葉だけではコミュニケーションは成立しないのです。
私たちは言葉だけを伝えることはできません。
言葉には、人生、人格、価値観、命令、指示、感情、考え、言葉以外のすべてがついてくるのです。
さて、先ほどの一つだけの本当のこと。
それは「私は趣味でチョコレートづくりをしています」です。
私がショコラティエの仕事を手伝っていることは横に置いておきましょう。
私の正体が、これらの言葉だけで分かりましたか?
いかがでしょう?
実際に会ってみなければ分からないのではないでしょうか。
「言葉」はツールであり、感情や意図、姿勢などの非言語的要素も含めて、初めて効果的なコミュニケーションが成立します。
表情、声のトーン、態度などが欠けると、誤解が生まれやすくなります。
【コミュニケーションで失敗する人の特徴③】感情的、衝動的にコミュニケーションしてしまう

人間には、自分を守るための自己防衛のメカニズムがあります。
批判を受けたり、攻撃されたと感じたりすると、情動的に反発してしまうことがあります。
このような突発的な反応や感情は、相手を敵視してしまい、コミュニケーション自体を敵対的なものに変えてしまいがちです。
私たち人間が生きていくための生存本能の一つある「突発的で衝動的な怒り」をコントロールすることは、かなり難しいことです。
また、突発的な怒りを感じたときに、それを鎮めようとする行為にも賛否があります。
なぜならば、怒りとは「大切なものに触れられたことにより起こる反応」で、鎮めるものではないからです。
ある心理学の研究で、「私たちは大切なものに触れられなければ、怒りを感じることはない」といった研究結果があります。
そこで、怒りを感じたときには、「触れられた大切なものを再確認する機会」と捉え、行動するエネルギーに変換します。
怒りに対処する心理学的な研究は、これからも驚きの発見を続けてくれるでしょう。
負の感情やネガティブな考えといわれるものには、人生に役立つこともたくさんあります。
ところが正しい心理学の知識がないと、ストレスや不安、怒りなどの心理的要因が、良質なコミュニケーションを妨げてしまいます。
負の感情や負の考えなどの心理的要因は、コミュニケーションを難しくしてしまうのは自明の理でしょう。
【コミュニケーションで失敗する人の特徴④】異文化のテクニックを使ってしまう

異なる文化のコミュニケーションスタイルは、意図せずに誤解や摩擦を生むことがあります。
例えば、アメリカの自己主張を強調するスタイルは、日本では控えめさや調和を大切にするため違和感があり、結果としてまわりから嫌われてしまうことがあります。
日本は、場を大切にする「ハイコンテクスト文化」。
アメリカは、直接、メッセージを伝える「ローコンテクスト文化」です。
ハイコンテクスト文化の日本では、コミュニケーションの多くが言葉以外の要素に依存しています。
つまり、背景、状況、関係性、過去の経験や習慣などの「文脈」が大きな役割を果たします。言葉にされていない部分を含めた「空気を読む」能力が求められます。
対照的に、ローコンテクスト文化のアメリカでは、コミュニケーションは主に言葉に依存します。
メッセージを伝える際、背景や文脈に頼らず、明確で具体的に表現されることが一般的です。
【コミュニケーションで失敗する人の特徴⑤】意見の違いを尊重しない

意見の違い、相違を尊重しないコミュニケーションは、良い人間関係が築けないばかりではなく、生産的な新しいことが生み出されません。
先ほどの上司と部下の場面です。
上司:「経理部から営業部に代わってもらうことになりました」
部下:「営業ですか…。口下手なのはご存じですよね」
上司:「だからこそ、協力してほしいんだ…」
部下:「経理志望で入社したので、このままでお願いします」
断られた上司は、部下の希望を尊重し、配置転換をやめるかもしれません。
また、上司の期待に応えなかった部下は、何かで埋め合わせをしようと考えているかもしれません。
「経理から営業への配置替え」という出来事では、上司と部下の意見に相違があります。
しかし、上司と部下が、会社・社会に貢献したい気持ちは同じではないでしょうか。
そんなときこそ、上司と部下が本音で話し合うことで、相違を統合する解決策が見つかるかもしれません。
例えば、部下が営業をやってみて、本当に無理だと思ったら経理に戻す約束をする。
さらに、経理のスペシャリストになるために、営業の経験が必要なことを伝え、期限つきの配置転換を提案する。
このように、相違を受け入れ話し合うことで、解決するための新しいアイデアが生まれる可能性があるのです。
あなたの相違を示せ、私の相違を歓迎せよ、 あらゆる相違をより大きな全体に一体化せよ。 それが成長の法則である。 相違の一体化は、生の永遠のプロセス、 つまり創造的総合、創造という最高の行為…… |
『相違を歓迎せよ』経営の神様、P.F.ドラッカーのマネジメントにも出てくる経済学者、メアリー・パーカー・フォレットの言葉です。
コロナウイルスのパンデミックが起きた2020年。
「コロナ禍の不自由な外出状態」vs「仕事の生産性向上」という相違から、「テレワーク」が定着してきました。
通勤時間と職場への距離をなくしたメリットは、今後もテレワークを拡大させるでしょう。
弊社は「コロナ禍で会場でのライブセミナーが禁止状態」vs「仕事の生産性向上」という相違から、「生産的なオンラインセミナーづくり」の工夫を続けています。
デメリットもありますが、全国どこからでも参加できるオンラインライブセミナーは、徐々に参加者の皆さんの支持を集めつつあります。
相違は歓迎し、統合することで、新しいものを生み出すチャンスになります。
意見の相違は恐れるものではなく、相互理解を深め、新しいアイデアを生み出す機会と捉えましょう。
対立ではなく、相違を前向きに受け入れる姿勢が効果的なコミュニケーションの鍵です。
【コミュニケーションで失敗する人の特徴⑥】上から目線のコミュニケーションに気づけない

無意識に「上から目線」で接すると、相手は自尊心を傷つけられたと感じることが多いです。
対等な立場での対話ができないと、信頼関係が築きにくくなります。
「上から目線」で接するとは、以下の状態ことです。
まわりを指導してしまう
科学的根拠に基づく心理学によると、求められていない助言、アドバイスは、人間関係を悪くしてしまう可能性が大きいのです。
一方的に指示・命令をする
「なぜ、人間は自由なのに、組織に入ると上司の指示・命令に従わなければならないのか?」と、講座の中で参加者に問いかけることがあります。
すると、こんな答えが返ってきます。
「会社に入ったらルールがあるから…」「上司の命令を聞くのが当たり前だから…」
経営の神様P.F.ドラッカーは、次のように述べています。
「リーダーは自己実現するために生まれてきた人間を社会から借りている。 |
要約すると、「部下を自己実現させる仕事が提供できないのであれば、上司が部下に対して指示命令する権利はない」ということでしょう。
約束を忘れてしまったり、まわりの意見を軽視したりする
真摯さに欠けている上司は、まったくと言っていいほど尊敬されません。
自分は正しいと信じ切っている
二項対立(二つの概念が矛盾や対立の関係にあること)が強い方は、まわりを傷つけてしまうことがあります。
二項対立とは、物事を正誤、善悪、成功失敗、このようにどちらかの枠に当てはめようとすることです。
私たちの人生の主人公は、過去の経験です。
例えば、「青信号は進め、赤信号は止まれ」「夫婦別性は賛成!反対!」など、今まで経験してきたことをもとに「正しい」と信じていることがあるのではないでしょうか。
このように、人は自分の考えを自分の過去に経験した枠組みにはめようとします。
渋沢栄一氏の名言です。
「四十、五十は洟垂れ小僧、六十、七十は働き盛り、九十になって迎えが来たら、百まで待てと追い返せ」 |
人生経験が90年もあれば、いろいろな出来事を枠にはめることで解消できるかもしれません。
しかし、40代、50代では、まだ何もわかっていないのかもしれません。
相手の意見を尊重しましょう。相違を歓迎しましょう。
【コミュニケーションで失敗する人の特徴⑦】相手を変えようとしてしまう

上司が口にする、部下に対しての要望です。
「もっと、責任感を持ってほしい…」
「もっと、やる気を出してほしい…」
「もっと、早く成長してほしい…」
実はこの三つは、すべて上司自身の能力不足を嘆いています。
それを部下に責任転嫁しているのです。
相手を自分の思い通りに変えようとすると、抵抗を受けやすく、関係性に亀裂が生じることがあります。
なぜならば、「責任感を持ってほしい…」は、上司の望みであって、部下が望んでいるとは限りません。
「やる気を出して」についても、「早く成長して」についても同じです。
上司と部下の望みが同じであればいいのですが、そうであることはめったにありません。
ですから、最初に部下の気持ちを尊重し、上司の期待を強要しない姿勢が大切です。
指示や命令などの言語情報は、コミュニケーションを成立させる一つの要素に過ぎない

ここまでお伝えしてきたとおり、指示や命令は言語的な情報伝達に過ぎず、それだけでコミュニケーションが成立することは一切ありません。
そして、「言葉だけ」を伝えることはできないことも学んできました。
発する言葉には、言葉以外のものすべてが含まれているのです。 
こちらは、印象派、ルノワールの作品です。
女性の柔らかさが伝わってきます。
国家『君が代』。リズムを思い出すだけで、厳かさを感じませんか?
小学校の校歌。思い出せますか?懐かしさがよみがえりませんか?
リズムだけで、当時の感情がよみがえりますよね。
このように、言葉は情報に過ぎません。言葉と一緒についてくるものが重要なのです。
それを「非言語」といいます。コミュニケーションとは、「非言語を知覚する」ことなのです。
知覚とは、「見る」「聞く」「感じる」ことを指します。
相手は自分の期待するものを知覚(見たい、聞きたい、感じたい)したい

人は、自分が期待しているものを知覚し、自分の先入観や期待に基づいてコミュニケーションを受け取る傾向があります。
そのため、相手が何を大切にしているのかを理解し、それに配慮してコミュニケーションすることが重要です。
部下が残業をしないで定時に帰ることを大切にしているなら、それを尊重しましょう。
部下が終電に間に合う程度の残業を希望するなら、それなりの仕事を任せましょう。
上司が将来、大学で教えることを夢見ているなら、一緒に応援しましょう。
実際に、上司の夢を実現させるお手伝いをして、超有名企業で名を馳せた知り合いがいます。
コミュニケーションを成功させたいなら、相手が期待することから始めるのも優れた選択肢です。
まとめ|コミュニケーションで成功するためのコツとは

コミュニケーションを成功させるためのコツ。
それは、今回ご紹介した「コミュニケーションで失敗する人の特徴」を手放すことです。
AIが提示したコミュニケーションで成功するコツは、一般的なコミュニケーションの注意点として参考になるでしょう。
しかし、コミュニケーションは、相手との関係性や状況、文化など、さまざまな要素によって変化します。
それぞれの状況に合わせて、最適なコミュニケーション方法を選択することが重要です。
日本初のコミュニケーション専門スクールとして20年の実績を持つ私たちは、コミュニケーションは相手が主人公であるということ、意見の相違を尊重すること、相手との関係性を築き、信頼関係を深めることが大切だと思っています。
そしてコミュニケーションは、学ぶだけでなく、実践することが重要です。
さまざまな経験を積むことで、より円滑な人間関係を築くことができるでしょう。