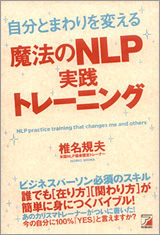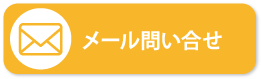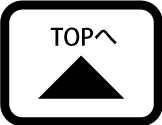自分との対話が人生を変える!自己肯定感を高めるセルフコミュニケーションの教科書
投稿日:2025年8月7日 / 最終更新日:2025年8月7日

最も大切なコミュ力!それは自分とのつき合い方、“セルフコミュニケーション”です。
「自分を責める。」
「満たされない。」
「自信が持てない。」
「よく誤解される。」
「まわりが気になる。」
これらはけっして悪いことでありません。
さらに、
「あの人みたいになりたい…」
「人間関係、対人関係が苦手…」
「自己啓発のために定期的な集まりが好き…」
「何かを求めてコミュニティーに参加している…」
このように思うことは、とても素敵なことです。
だけれど、それらで思い悩んでしまうなら、それはよいこととは言えないでしょう。
だって、人間は苦しいことなんてしたくないはずです。
苦しい選択をしているのは、何かの歯車がズレているのかもしれません。
人間は、価値あることを分別できる生き物。
苦しいことで悩み続ける時間がもったいないと思いませんか。
もっと素敵な生き方があるはずです。
さて、先ほどの例はすべてセルフコミュニケーションのテーマです。
自分とのコミュニケーションで満たされてはじめて、まわりとの関係性で悩まなくなります。
そして、自分の人生を、自分でデザインできるようになります。
もちろん、社会から応援されて…。
目次 [閉じる]
日常の出来事を「ストレス」、もしくは、「驚き」と認識するのか?

よりよく生きるのに、もっとも重要なのは自分とのコミュニケーションではないでしょうか。
そんなことは言うまでもないかもしれません。
毎日が思い通りにならない出来事の連続…。
これは誰しも同じではないでしょうか?
それをストレスとして悩む方向に向かい、的外れな解決策を見つけようとしますか?
それとも、思い通りにならない出来事を驚きとして学ぶ機会にし、自分の認識を広げていきますか?
その違いは、“人生に大きな違いをもたらす”という言葉では、表しきれないかもしれません。
これらは、ストレスか?驚きか?

セルフコミュニケーションが下手な人の訴えの例をみてみましょう。
人間関係・対人関係のテーマ
- 「言いたいことを言えない、我慢する」
- 「何を話していいのかわからない」
- 「誰といても気を遣って疲れる」
- 「嫌われるのが怖い、嫌われないようにしてしまう」
- 「分かり合えない、孤独を感じる」
- 「あの人がどう思っているかばかり気になる」
このように、他人との関わり方を学ぶ機会はストレスなのでしょうか?
対処法として、闘う・逃げる・隠れるの『闘う・逃げる反応』を駆使することもできます。
そして、一人ひとり、宇宙レベルの個性と出会っている『驚き』として認識し、自己中心的な社会の中で生きる厳しさを知り、まわりをねぎらえる存在になることもできます。
避けるのか。愛を育てる機会にするのか。
どちらで生きればいいでしょうか?
孤独・不安に関するテーマ
- 「不安になる」
- 「SNSが止められない」
- 「何もしない時間が嫌い」
- 「一人でいると落ち着かない、何かしていないと怖い」
不安になるのは自然なことです。
不安になるのは仕事中?不安になるのは、寝起き?
※病気レベルなら、お医者さんに相談してくださいね。
不安というものは避けるものではなく、何かを教えてくれているサインだと考えた方が役立ちます。
スタンフォード大学の心理学者ケリー・マクゴニガル(Kelly McGonigal)は、著書『ストレスを力に変える教科書(The Upside of Stress)』や講演の中で、不安やストレス反応を「敵」ではなく「味方」として捉え直す視点を提示しています。
「不安=悪いこと」という思い込みが、苦しみを増やします。
私たちは「不安だからダメだ」と考えると、余計に緊張や自己否定が強まります。
反対に、「ワクワクのサインだ」と捉えれば、同じ不安の生理反応がパフォーマンス向上につながるのです。
重要なことです。
不安という出来事に問題があるのではありません。
不安というものを、どのように自分で認識するのか?に問題があるのです。
問題は、不安なことではなく、不安への自分の認識です。ということは、セルフコミュニケーションの問題なのです。
人生の方向性や選択に関するテーマ
- 「自分が見つからない」
- 「使命が見つからない」
- 「何がやりたいのかわからない」
- 「自分の決断に自信が持てない」
- 「他人の意見に振り回されてしまう」
自分が見つからないのは、自分というものを知らないからです。
「?????」でしょう。
たとえば、「自分が見つからない」と思っているのは誰なのですか?
そう。それが“本当の自分”です。
だから、“本当の自分”を見つけることは難しいでしょう。
ただし、“本当の自分”に触れることはできるのです。
「心理学者の数だけ心理学がある」と言われるこの分野で、「自分」、すなわち“自分とは何か”を、唯一無二の科学的答えとして示した者を私は知りません。
だからこそ、不滅の哲学者・池田晶子さんの言葉が、私たちに問いかけてくれます。
「自分とは、説明されるものではない。ただ、『在るもの』である。」
その『ただ在るもの』に、私たちは触れることができる。
それこそが、セルフコミュニケーションの醍醐味です。
感情コントロールに関するテーマ
- 「イライラする」
- 「自信が持てない」
- 「自分を責めてしまう」
- 「妬みや劣等感が消えない」
生きていれば感情がともないます。
このテーマの解消には、『仏教のたてまえ』という考えが役立ちます。
「まずこころがあり、こころがあるから世界があり、世界があるから衆生がある。その衆生にそれぞれ心がある」
仏教学者の紀野一義さんのことばです。(※『私の歎異抄』 P26)
ひらがなの「こころ」とは、自分を超えたすべてがある宇宙。
その中に世界がある。
そして、衆生という一人ひとりの人間が存在して、漢字の「心」がある。
大切なのは、人間レベルの「心」と宇宙レベルの「こころ」の働きはまったく違うこと。
人間レベルの「心」は、常に揺れ動く無常。
宇宙レベルの「こころ」は普遍。
いつも「善」に導こうとする。
たとえば、「イライラする」とは、自己中心的な「心」が反応しているときではないでしょうか?
もし、「イライラする」が、みんなにとって善い選択をする機会とするならば、イライラする出来事に問題があるのではなく、そう認識してしまう自分の方にあるのかもしれませんね。
「イライラする」「自信が持てない」「自分を責めてしまう」「妬みや劣等感が消えない」などの負の感情は、“ストレス”ではなく“驚き”という、奇跡の感情「ありがとう」に出会った軌跡であると受け取ってみましょう。
行動習慣のテーマ
- 「誘われると断れない」
- 「やめたいことがやめられない」
- 「付き合いに時間を使ってしまう」
- 「つい飲みすぎ、食べすぎてしまう」
- 「予定がないとスケジュールを埋めたくなる」
これらのテーマの源は察しが付くでしょう。
それは、自分を大切にする方法を知らないのでしょう。
十分に自分を愛せて、それで貢献することが理想のはずです。
だって、自分を愛し、それを実感できなかったら、相手にそれを提供できませんよね。
“自分を愛する”ことをしてみましょう。
自分と「心」と、大いなる存在の「こころ」で会話するということが、本当の自分に触れることです。
「心」からの問いが、みんなにとって善いことであれば、「こころ」はこたえを届けてくれます。
時間がかかっても……。
もっとも重要なコミュ力。「セルフ(自分との)コミュニケーション」の研き方

たとえば、誰かと意見の食い違いが起きたとしましょう。
自分が相手に言いすぎてしまい、「さっきは言いすぎてしまった。ゴメンなさい。」と素直に伝えたいと思ったとします。
そのとき、この三択だとしたら、どうしますか?
- 思ったことを素直に伝えて謝罪する
- 相手もそうだったのだから放っておく
- 相手からの謝罪を待つ
これがセルフコミュニケーションの力の研き方です。
私だったら、自分の腹に据えかねることがあっても、素直に相手に「言いすぎてしまった」ことを謝罪の気持ちとともに伝えます。
なぜならば、そのほうが相手と自分にとって、気持ちのいいことだろうと考え、みんなにとって善い選択だと思うからです。
それだったら、言いすぎないようにすればいいのですが…。
思ったことは言わない方がいい

一人では生きていけません。
どこかで誰かと関わります。
必ず「心」の感情が働きます。
人間関係、対人関係において、怒り、妬み、自信喪失、怖れ、罪悪感、自責…。
私が指す「心」から、いろいろな感情が湧き起きます。
そのときに、表情や言葉に出てしまいます。
出ない人もいますが、出ない人はなぜでしょうか?
そういう感情が出ない人は、大人なのでしょうか?
そうではありません。
そういう人は、『静けさ』という感情をエレガントに扱っている人です。
大人の人間とは、驚くこと(一般的なストレス)に対して、思ったことをその場で言うことはないでしょう。
なぜなら、気まずくなることを知っているから。
そして、「こころ」からのヒントを待つことができます。
いつもにこやかに生きている
私たち人間は、大人や親兄弟の様子を観察しながら育ちます。
その過程で、人格、性格がつくられるのでしょうか?
「心」の特徴が育まれます。
みなさんのまわりにも、言い争いに巻き込まれにくい人がいるでしょう。
それは、人間関係・対人関係において、自然にセルフコミュニケーションができる人です。
だからもし、人間関係・対人関係におけるコミュニケーションで、エレガントな立ち振る舞いを身につけたいなら、彼らをモデルにするといいのではないでしょうか。