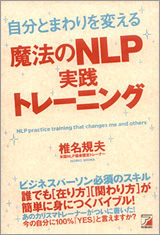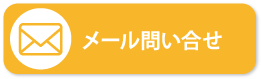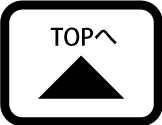コミュニケーション能力を上げるには? 専門家が教える人間力と実践的なスキル
投稿日:2024年1月13日 / 最終更新日:2025年9月3日

コミュニケーション能力と言っても、求められる範囲は広いです。
この記事では、職場の人間関係・対人関係、恋愛や友人関係での悩み、日常会話のスキルアップ、心理状態との関連性などに役立つ、実践的な方法をお伝えします。
目次 [閉じる]
コミュニケーション能力とは何か。 まだ新しい“文化”としての位置づけ
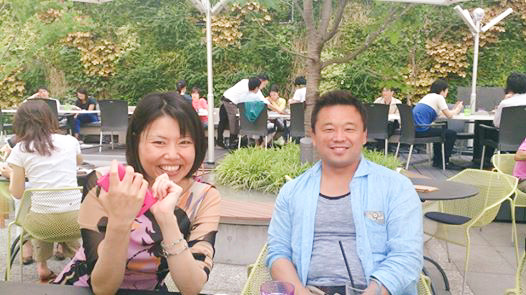
コミュニケーションの悩み
コミュニケーションの悩みは様々です。たとえば、
- 「日常会話が苦手…」
- 「コミュニケーション能力がないって言われた…」
- 「言いたいことがうまく伝わらない…」
- 「人間関係、対人関係に疲れた…」
職場での悩み。
「上司や部下との会話が続かない」
「自分の意見がうまく伝えられない」
人間関係、対人関係での悩み。
「相手の気持ちを読みすぎて疲れる」
「嫌われたくなくて本音を言えない」
「沈黙が怖くて無理にしゃべってしまう」
プライベートでの悩み。
「人と関わると疲れてしまう」
「恋人や家族に気持ちを伝えられない」
職場での会話のぎこちなさや、自分の意見をうまく伝えられないもどかしさ。相手の気持ちを読みすぎて疲れたり、本音を言えずに悩んだりする人間関係。こうした悩みは尽きないものです。
しかし、コミュニケーション能力は、私たちの人生を豊かにするために不可欠な力です。
一流のコミュニケーターに共通するスキル
私たちは2004年にコミュニケーションスクールの前身を立ち上げ、以来、約20年にわたり指導を続ける中で、ある重要な事実に気づきました。それは、一流のコミュニケーターたちが、分野は違っても驚くほどシンプルな共通のスキルを大切にしている、ということです。
たとえば、次のような達人たちです。
・子育て上手な母親
・優れた経営者、ビジネスリーダー
・トップ営業マン
・プロコーチやカウンセラー
そんな達人たちが共通して持つ本質的なコミュニケーション能力と、それを身につけるための実践的な方法をお伝えします。
日本における「コミュニケーション」という概念
「コミュニケーション能力が大事」と言われるようになって久しいですが、改めて「そもそも何だろう?」と正面から答えられる人は、意外と少ないのではないでしょうか。
なぜなら、日本に『コミュニケーション』という概念が入ってきたのは戦後、1950年代以降だからです。それまでの日本文化には、『以心伝心』のように言葉を介さない概念はありましたが、学問としての発展は1980年代からでした。
この新しい文化を体系化した人物として、20世紀最高の知の巨人、P.F.ドラッカーがいます。彼は世界的ベストセラー『マネジメント』で、コミュニケーションをシンプルに定義しました。
『コミュニケーションとは、自分以外のものと関わる能力』
これは、実に単純でありながら奥の深い言葉です。誰もが「自分以外のもの」と関わりながら生きているからです。この「関わる能力」こそ、現代のあらゆる場面で求められるコミュニケーション能力の核心です。
「知識」を超えた「知恵」
現代の教育や仕事の場では、知識やテクニックが重視されがちです。しかし、どれほど大量の情報を抱えていても、それを他者との関係の中で活かせなければ、それは単なる蓄積にすぎません。
江戸時代の思想家、荻生徂徠(おぎゅう・そらい)は、「学問とは人倫の学である」と説きました。「人倫」とは、人と人との関わりを指します。徂徠にとって、学問とは単なる知識の蓄積ではなく、人と関わりながらより良く生きるための「知恵」でした。
この視点は、現代のコミュニケーション能力にそのまま通じます。どれほど豊富な知識やスキルがあっても、それを他者に伝え、互いに理解し合う「人と関わる力」がなければ、社会で活かすことはできません。
徂徠の言葉を現代に置き換えれば、コミュニケーション能力とは、人との関わりを通じて育まれる人間力だと言えるのです。
この知恵を、達人たちは驚くほどシンプルな力で実践しています。
- 子育て上手な母親は、子どもの小さな声に丁寧に耳を傾けます。
- 優れた経営者は、社員の想いを受け止めます。
- トップ営業マンは、顧客の言葉にならない不安を汲み取ります。
- プロのコーチは、相手の沈黙すら尊重します。
彼らが共通して持つのは、特別なテクニックではなく、「相手の話を聴く力」「相手を尊重する姿勢」「素直でエレガントな自己表現」といった、誰もが持ち得るシンプルな力なのです。
コミュニケーション能力を実践する心構え
コミュニケーションとは、互いの考えや気持ちを交換する、双方向の意志疎通です。その成功は、「相手に受け取ってもらうこと」にかかっています。
そのため、以下の3点は避けなければなりません。
- 相手を操作すること
- 負の感情を向けること
- 自分の考えを押しつけること
これらは一方通行であり、コミュニケーションではなく、単なる命令や強制に過ぎません。
ドラッカーは「コミュニケーションとは、組織の在り方そのものである」と述べました。これを個人に当てはめると、コミュニケーション能力とは、その人の在り方そのものと言えます。あなたが話す言葉は、あなた自身の価値を決定すると言っても過言ではないのです。
ストレスは「学び」の機会
同じ出来事でも、それをどう「受け取るか」によって意味は変わります。上司に叱られたとき、「嫌われた」と否定的に受け取る人もいれば、「自分に目を向けてくれている」と肯定的に捉える人もいます。
そして、人生に「失敗」はありません。あるのは**「学び」**だけです。次にうまくやるための練習だと捉えれば、全ての出来事は私たちを成長させる機会となります。この姿勢こそが、コミュニケーション能力を高める第一歩です。
コミュニケーション能力の可能性とAI時代、人生100年時代に求められるスキル
「コミュニケーションが絶大な威力を発揮した場合には、
受け手の人格、価値観、信条、野心などを根こそぎ変える。」
P.F.ドラッカー
AIが発展する時代だからこそ、人間が持つべきコミュニケーション能力はより重要になります。特に注目すべきは**「Being(存在)レベル」**のコミュニケーションです。
AIは、言葉にできない人間の使命、強み、価値観といった「存在」そのものを深く理解することはできません。なぜなら、それらは言葉を超えたところに実在するからです。
Beingレベルのコミュニケーションは、相手の存在そのものに働きかけ、深い信頼関係を築くスキルです。
例えば、部下が仕事の遅れを相談してきたとき。ただ叱るのではなく、「君は正直だなぁ」「そんな君と仕事ができて安心だよ」といった言葉をかける。そうすることで、部下は安心し、リーダーへの信頼感を深めます。
このようなシンプルで本質的なやり取りが、相手のモチベーションを高め、潜在能力を引き出すのです。テクニックばかりに頼るのではなく、この土台となるBeingレベルのコミュニケーションを身につけることが、これからの時代に求められます。
優れた人材を育てる4つの能力
私たちは、時代が求める以下の4つの能力を重視し、コミュニケーション能力のトレーニングを提供しています。
気づく力
相手や周囲の状況、さらには自分自身の内面にまで「気づく」能力です。これは「気配り」や「思いやり」として表現され、人間力の土台となります。
寄り添う力
相手のプロセスや努力を認め、「寄り添う」姿勢です。この力は、関わる人々のモチベーションを維持し、良好な関係性を築きます。
関係性を構築する力
多様な価値観を持つ人々の中で、良好な「関係性」を築く能力です。専門性を持つスペシャリストほど、この力がなければ成果を上げることは困難です。
自己開発する力
問題や困難を「成長の機会」と捉え、乗り越えるための「自己開発」を続ける力です。この力こそが、社会に求められるリーダーシップの基盤となります。
コミュニケーション能力を身につけるための前提
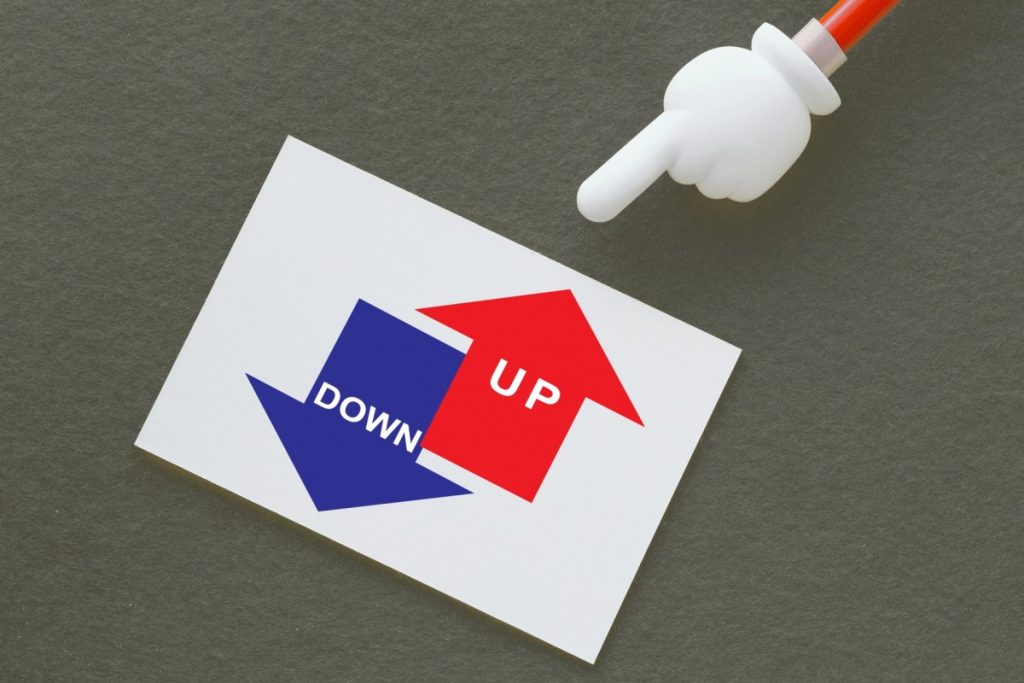
本当に求められるコミュニケーション能力を身につけるには、その前提となる心構えが重要です。
自分一人では完結できないという理解
コミュニケーションは、相手がいて初めて成立します。「人は他者とともに生きる存在」という事実を受け入れることが出発点です。
知識や情報は手段であるという意識
知識は、相手を理解し、支えるための道具です。人との関わりの中で実践し、知恵へと昇華させて初めて価値が生まれます。
不完全さを受け入れる:
完璧な言葉や振る舞いを求めるのではなく、誠実さを大切にすることです。「失敗してもいい」というチャレンジ精神が、自然な関わりを生み、信頼を築きます。
究極のコミュニケーション能力「無私の精神」

何より大切なのが、「無私の精神」です。自分の利益や自己主張ばかりを優先すると、コミュニケーションは損得勘定の駆け引きに変わります。
相手の立場に立ち、相手の思いや状況を尊重する。この無私の姿勢があってこそ、信頼と共感が育まれるのです。無私とは、自分を消すことではなく、相手と共により良い関わりを築こうとする心を持つことです。
私たちトレーナー協会では、この「無私の精神」と「Beingレベル」のスキルを最も重要なものとしています。これらのスキルは、一度身につけば一生もののスキルとなり、自分と周囲の自己実現に深く関わる存在になれるでしょう。
この普遍的なコミュニケーション能力こそ、時代が変わっても私たちを支え続ける力なのです。