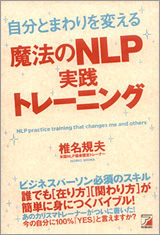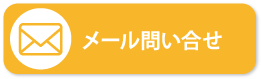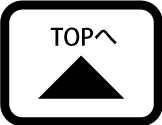誰もがはじめての人生を真剣に生きている
投稿日:2025年11月17日 / 最終更新日:2025年11月18日
このままでは年を越せない
「今年のうちにやらなければならないことがある。これでは年を越せない。新しい年を迎えられない」。あるコミュニティでは、こうした話題で持ちきりであるという。「どうすればよいのか」と相談を受けた。このままでは年を越せないと切羽詰まっているらしい。こういうときは、「可能性を追いかける、美しい生き方ですね」とでも声をかければよいのだろうか。
しかし、そもそも「来年」という抽象概念を、われわれは一生体験することができない。今は2025年11月であるが、来月になれば、それは「今年の12月」になる。そして年が明け2026年になれば、それは再び「今年」になる。
おちゃらけて「このままでは年を越せない」と言う者に、「大丈夫です。永遠に来年は来ませんよ」と告げたとしても、冗談としてすら受け取ってもらえないだろう。おかしなことを言うオッサンと思われるのがオチである。疑う者は肩身が狭く、疑わない者は真実が遠い。
シンプルな成功法則
流行語大賞の年間大賞「いつやるの? 今でしょ!」は2013年のことである。東進ハイスクールの林修氏の決め台詞として広く知られ、その年に大きなブームとなった。
明日やろう。明日の予定。今日はここまで、残りは明日。人間の集中力には限界がある。体を休め、生産性を考えるならば、作業を明日にまわすことは自然で合理的な判断である。
しかし、これもよく考えてみる必要がある。「明日」という日は絶対に来ない。日が変わった瞬間、それは明日ではなく「今日」になる。当たり前のことだが、われわれが実際に体験できるのは、つねにこの「今」だけである。
それでも、もし明日という概念を信じることができなかったら、われわれ人間はどうなるだろうか。毎日、「今日までが命なのかもしれない」と怯えながら生きざるを得なくなる。抽象概念とは、人間を支える素晴らしい仕組みである。
あまり深く考えすぎる必要はない。答えが出る種類の問いでもない。ただ、「明日がある」と信じることで平静に生きられるのなら、一生訪れることのない明日を信じながら生きるという、人間らしい生き方の方が楽なのではないだろうか。
こうしたことを考えることもなく日々を生きる者にとって、林修氏の「いつやるの? 今でしょ!」が流行語年間大賞となった意義は大きい。「行動すべき瞬間はつねに今である」という当たり前の事実を、久しぶりに思い出させてくれたからである。
本気で悩んでいます
20代前半で拒食症を発症したお嬢さんを育てている母親がいる。元気がなさそうなので「悩んでいそうですね」と声をかけたところ、「真剣に生きているから、本気で悩んでいます」と返された。
まるでこちらが真剣に生きていないかのようにも聞こえる。そんなことは気にしないが、精一杯生きている者からすると、悩むことを止めてしまった人間を見ると誤解してしまうのかもしれない。悩むことでその問題が解決すればよいのだが。
言い訳はしない。しかし事実として、誰もが真剣に生きているはずである。少なくとも、呼吸し、鼓動し、消化してくれる体の不随意運動は、私たちの優柔不断な意志とは違い、つねに一所懸命に人生を応援してくれている。
こんなことを言うと、先ほどのお母さんに叱られそうであるが、自分の意志ではどうにもならないことが起きる。病気とは、そういうものなのであろう。では、自分の意志ではどうにもならない病気とは、われわれに何を教えようとしているのだろうか。
「手のひらを太陽に」の誕生秘話
先日、黒柳徹子さんの「徹子の部屋」で、作詞家のやなせたかし氏が出演した回の再放送を見た。そこで、代表作「手のひらを太陽に」の誕生秘話が語られていた。やなせ氏は4歳のとき父が他界し、若かった母はすぐ再婚し、彼は父方の叔父夫婦に引き取られた。唯一の弟は戦死している。
誰もが知る明るいメロディーの裏に、生きることへの痛切な思いと、絶望の中から見いだされた希望が込められていたのである。
この歌は明るい曲調とは裏腹に、やなせ氏が最もつらく、仕事がなかった時期の体験に基づいている。「アンパンマン」で有名になる以前の彼は、漫画の仕事がほとんどなく、悲観的な状態に追い込まれていた。
暗い仕事部屋で懐中電灯を照らしながら作業していたある日、その光に手のひらをかざし透かしてみると、皮膚の下を真っ赤な血潮が流れているのが見えた。
その瞬間、「自分はまだ生きている」「体の中に熱い血が流れている生きた人間である」という強い実感と喜びを得た。「自分は落ち込んでいるのに、血はがんばっている。自分もがんばらなくては」と奮い立ったという。この体験を詩にした際、「懐中電灯」では語呂が悪いという理由で、「手のひらを太陽に」に置き換えたそうである。
歌詞について、やなせ氏は「生きているから悲しいんだ」を一番にし、「生きているからうれしいんだ」を二番にした理由を、「死んでしまえば悲しみも喜びもない。生きているからこそ、つらさや痛みがある。それは生きている証である。そして喜びより悲しみの方が強いから、悲しみを先に置いた」と語っている。
拒食症のお嬢さんを前にして、「人生は誰もが初めてで上手くいかないことがある」と伝えても、そんなことは分かり切っている。かえって感情を逆なですることになりかねない。子の苦悩に対して親がどう振る舞うべきか。まして周囲の者は、たとえ善き試練の時間であると気づいていても、それを言う必要はまったくない。求められない経験談は受け取る余裕がないだろう。
うつ病のリレー
うつ病になったとき、先に経験し乗り越えた友人に、どうやって乗り越えたのかを聞きたくて相談したことがある。
彼は「時間がくれば治る。俺はそうだった」とそっけない返事であった。それが優しさであったのかどうかは分からない。しかし、そのときは話を聞いてもらえただけでも気が晴れた。同じ経験を持つ者からの言葉は、症状が変わらなくても嬉しいものである。「いつまで続くのか。いつになったら治るのか」と思うことも、少しの間は忘れられる。
彼からは、今すぐ役立つ対処法を一つ教えてもらい、それで助かったことがある。うつ病になると過呼吸を起こすことがある。過呼吸は酸素を吸いすぎているというより、二酸化炭素を吐きすぎることが問題となるらしいのだが、とにかく突然息が苦しくなる。その対処法を友人が教えてくれた。車の運転中に過呼吸を起こしたら一大事である。
対処法とは、薄いビニール袋を用意し、過呼吸になったら鼻と口を覆い、袋を膨らませたり萎ませたりしながら呼吸するというものだ。
数日後、その方法が役立った。薄暗い夕方、行きつけのガソリンスタンドの交差点で過呼吸になってしまった。急いで駐車場に停め、ビニール袋で呼吸を繰り返した。そこへ怪しげな大男が近づいてきて、大声で「シンナーなんて吸ってんじゃねぇ」と怒鳴った。
こちらは呼吸が苦しくて反論できない。ビニール袋と虚ろな目は、確かにラリっているように見えたのかもしれない。怒鳴られ続け、後から事情を説明したものだ。40年前は、うつ病はメジャーな病ではなかった。過呼吸を知っている人も、今でも多くはないのではないか。信じてもらえたかどうかは分からない。
どうやってうつ病が治ったのか
さて、どうやって治ったのか。発症は、結婚式が3か月後に迫る頃であった。結納が済み、婚約者であった彼女に「こんな精神状態の自分と結婚するのは、考え直した方がいいのではないか」と真剣に伝えた。すると彼女は、「もし働けなくなったら、朝晩仕事して家庭を支えるから大丈夫」と言った。彼女は何かを知っていたのだろうか。目の前の人に貢献する言葉は、いつも優しい。ただし、本気の姿から生まれた言葉でなければ、相手には響かない。
外出できなくなっていた私を心配し、友人夫婦が映画に誘ってくれた。忘れもしない『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART II』である。映画館まではたどり着いたが、席に着いてから上映が終わるまで、火事になったときにどう逃げるかばかりを考えていた。パニック障害を併発していたのかもしれない。
母は、何かに憑りつかれたと思ったのか、お祓いに連れていった。父は、息子のうつ病が信じられず、ただ仕事をしたくない甘えだと決めつけ、厳しく接した。恨んではいない。経験したことがないことは分からないのである。ありがたいことである。
早く治りたくて本を漁った。そこには「自分のことばかり考えるのがうつ病。周りの幸せを考えられるようになれば回復に向かう」と書かれていた。完治した今なら、その通りであると思える。しかし、その状態にいる者には重すぎる真理であった。真実とは、必要なときでも受け取れないものである。深刻な状態が3年続き、その後2年ほど引きずった。良い経験となった。
その後、数名の友人がうつ病になった。電話がかかってきて、「どうやって治したのか」「元気に戻れたのか」と問われた。当時、私は「いずれ役立つ経験になるよ」「ゆっくり休めばいい」と伝えた。
そして30年後、うつ病の後輩たちと再会したとき、「あの時は相談に乗ってくれてありがとう。それだけで気分が軽くなった」と言われた。求められたときの、ほんの一言、二言の言葉。それでよかったのである。寄り添うとは、そういうことなのだと知った。
娘の拒食症を克服した仲間
小学校6年生、身長143センチ、体重18キロ。拒食症であり、医師からは「一生治りません」と見放されたそうである。
そのお母さんに、どうやって乗り越えたのかを根掘り葉掘り聞いた。しかし母であっても娘本人ではない。お嬢さん自身も、どうやって乗り越えたのか分からないのかもしれない。お母さんに数回インタビューする機会があり、完治していくストーリーを何度も教えてもらった。その詳細は彼女のブログを参考にしていただくとよい。(https://www.kosodate.ne.jp/)
その母娘の物語に、特に心に残ったエピソードがある。母親は、いつか治ると信じて、冷蔵庫にお嬢さんの大好物であるゼリーをずっと用意していた。そしてお嬢さんが拒食症から解放されたその日、ゼリーを食べ、そこから回復が始まった。
信じられないほどである。未来を信じて準備しておくとは、まるでその日を知っていたかのようである。完治したお嬢さんが母に伝えた「お医者さんも私も治るなんて思っていなかった。でも、お母さんだけは信じてくれた。ありがとう」という言葉を聞いたとき、われわれ人間には理想を現実にする力があるのではないかと感じた。
そして母は、娘が乗り越えるのを言葉で促さなかった。やさしく見守ることだけでも、言葉と同じ変容が起きるのではないか。どんなに辛いときでも、理想を思うことは、その方向へ導いてくれる。自分自身も、家族も、友人も、仲間たちも、より良い未来を理想として描き、それを実現してきた。
それに比べて。
病気にする言葉
医師の「一生治りません」という言葉。その影響を医師はどれほど考えているのだろうか。うつ病になったときのことを思い出す。仲間とゴルフをしていたが、前半戦で過呼吸を起こし、中規模の病院に行った。診察、触診、CT、レントゲン、血液検査。暇だったのか、あらゆる検査をされた。診断結果は「どこにも異常がありません」。安心して会計を待っていた。
すると薬局からフルネームで呼ばれ、「薬が出ていますよ」と言われた。「先生は異常ないと言っていました。何の薬ですか」と尋ねると、「うつ病の薬です」。
その瞬間、体と心が重くなり、動作が緩慢になった。まるで自らうつ病を演じ始めたようである。医師は言葉の力を知っているのか。私は知らなかった。そして後に、その力を思い知らされ、言葉を扱う仕事を生業とする道へ進む僥倖に恵まれた。言葉という魔法を学べる、生涯をかける価値のある瞬間の始まりであった。
最後の通院
毎日、眠い。体調が極端に悪いとは思わなかったが、60歳を過ぎたこともあり、念のため近所の医者に行くことにした。自ら病院に行くのは10年ぶりである。ワクチンも嫌いで、インフルエンザにもかかったことがない。コロナに感染したと思われる時も2回ほどあったが、診断を受けずに数日寝れば治った。病院が嫌いで、会社の健康診断も20年ほどパスしてきた。
あるとき、偶然先輩と会い、この病院に行く話をした。すると先輩は「俺はあの病院、出入り禁止なんだ」と言った。痛風で通院していたらしいが、自分の不摂生で半年経っても改善が見られず、医師から「自分の体を大切にしない人は来ないでくれ」と言われたらしい。あの女医である。
さて、何かあればこの病院に行くと決めていた。久しぶりの待合室でマスクをさせられ座っていた。すると次に呼ばれそうな老婆がいた。車椅子に乗り、鼻から点滴を受けている。小さく唸るように呼吸が苦しそうで、家族が寄り添っていた。その姿を見て、ここが本当に来るべき場所なのかと一瞬思った。
やがて順番が来た。老婆と入れ違いになるように、診察と別室での検査が進んだ。最後の診断は老婆が先であった。医師は時間をかけ、ほとんど言葉にならない老婆の話に耳を傾けていた。聞き耳を立てていたわけではないが、どうやら老婆にとって「最後の通院」のようであった。これからはホスピスに向かうのか。家にも帰らないという話が聞こえた。
医師は優しい声で「お祖母ちゃん。ありがとう。元気で暮らすのよ」と告げた。不思議なほど、その言葉に嘘がなかった。
その瞬間、老婆のどこに力が残っていたのか。突然、大きな声を張り上げた。
「〇〇医院の益々の発展を祝って、バンザイ! バンザイ! バンザイ!」
小さな院内に、その声が響き渡った。
老婆と医師の間にどれほど深い信頼があったのか。胸を打たれた。老婆はこの町医者に「お別れ」をするために、家族にお願いして連れて来てもらったのだ。感謝を伝えるために来院したのだ。美しい老婆と、医師、看護師、そしてスタッフたち。その光景が焼き付いている。
食事療法
毎月1回ずつ通院し、3回目の検査結果を聞きに行った。すると、「先月の検査結果だけれど、まったく数値が改善していません」「食事のルールは守っていますか」「間食していませんか」
思わず「えぇ、間食しちゃダメなんですか。そんなの聞いてませんよ」と反論してしまった。医師は「最初に紙を渡して言ったでしょう。もう一度説明するから、ちゃんと聞いて」と不機嫌になった。先輩と同じように出入り禁止にならなければよいのだが。
「もう一度検査しましょう。数値が変わらなければ薬を増やします」と言われ、次の検査までの1か月間、近所の農園で作られる大好きなシャインマスカットを断ち、アイスクリームも断ち、ほぼ間食をやめた。
翌月の検査。数値は改善していた。すると待合室にいた私のところまで医師が飛んできて、「やればできるじゃん。薬は増やさないわ」と言い、嬉しそうに診察室へ戻っていった。その姿を見て胸が熱くなった。
この医師は「自分を大切にする患者」が好きなのである。患者が自分で自分を世話するように導く医師なのだろう。だから毎日お酒と旨いものばかりで生活している先輩は出入り禁止になったわけである。
自分の病気を治せるのは自分だけである。しかし、そばにいる者、家族や仲間が病になれば、本人以上に心を痛め、思いやりをもって接してくれる。そのレベルで考えるなら、悩んでも解決しない病であっても、周囲に心配されていることに気づくだけで、人は健康を取り戻し始めるのかもしれない。生きる力が湧くのかもしれない。
人生を生ききる
病院で万歳三唱した老婆の声には、人生を十分に生ききった力強さが響いていた。
人は、どこまでも、結局は一人で生きてゆくしかないのかもしれない。しかし、その人生には、どれだけの無私で関わってくれた愛が共にあったのだろうか。であるならば、自らが無私となり、目の前の人を喜ばせる人生は、決して悪くはないのではないか。
善く生きるとは、まさしくそういうことであろう。
気の利いた言葉が出なくとも、「大丈夫だ」という気持ちでただ寄り添うだけでもいいのかもしれない。余計なお節介よりも、目の前の人の生きる力を信じることだけでも十分ではないのか。
もちろん、気の利いた言葉があれば、それに越したことはないが。