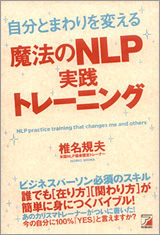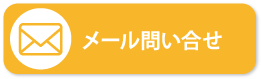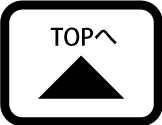コミュニケーションで人間関係を円滑にする方法【完全ガイド】
投稿日:2025年7月24日 / 最終更新日:2025年7月25日

「上司と会うのが憂うつ…」
「年上の部下とどう接したらいいの…」
「やりがいのある仕事だけれど、人間関係が…」
「分かってもらえない…」
「話を聞いてもらえない…」
「私は、この場所にいなくてもいいのではないか…」
このように、職場の人間関係で問題を抱える方は後を絶ちません。
そこで今回は、人間関係を良くするコツを解説します。
人間関係が上手くいっていることの前提は、お互いが相手を理解し合えているということです。
しかし、私たち人間は、誰しも完璧ではありません。
相手を理解し尽くせないという現実に向き合う姿勢も大切です。
「相手を理解すること」と「相手を理解し尽くせない現実に向き合い続けること」、この二つを理解することが、人間関係を良好にするコミュニケーションの基本姿勢です。
目次 [閉じる]
なぜ、人間関係でコミュニケーションが重要なのか?

はじめに、人間関係においてコミュニケーションが重要な理由を解説します。
人間関係が幸福感や仕事の成果に与える影響
人間は社会的な生き物です。だから、他者との関わりが個人の幸福感や満足感に直接影響します。
良好な人間関係は、メンタルヘルスの向上やストレス軽減に寄与し、結果として生活の質を高めます。
職場においても、信頼できる人間関係は、チームワークの向上や個人の業績を押し上げ、組織全体のパフォーマンスにプラスの影響を与えます。
コミュニケーションの役割とは
コミュニケーションは、単なる情報交換ではなく、感情や意図を共有し、理解し合うための行為です。
質の高いコミュニケーションを行うことで、誤解や衝突を避け、互いに安心感を持ちながら関係を深めていくことが可能です。
逆に、コミュニケーションが不足したり、質が悪かったりすると、誤解や不信感が生まれ、人間関係にひずみが生じます。
これが積み重なると、ストレスや孤立感を招き、生活の質を低下させる要因となります。
良好な人間関係とは
良好な人間関係とは、一人ひとりを一人格として尊重し、関わり続けることです。
信頼と尊敬に基づいた関係であり、互いに安心して意見を交換できる状態を維持できることも大切です。
お互いの違いを認め合い、感情や考えを率直に伝え合えることも、良好な関係の重要な要素です。
また、問題が発生した際には建設的に解決し、お互いの成長を支え合う関係性が理想的です。
人間関係とコミュニケーションの基本

人間関係とコミュニケーションは、私たちの日常生活や職場での心理的安全性、幸福感に直結する重要な要素です。
相手との信頼関係を築くには、「すれ違い(相違)」を「機会」にするコミュニケーションが基本です。
『現代経営の母』とよばれるメアリー・パーカー・フォレット女史は、次のように記しています。
「あなたの相違を示せ、私の相違を歓迎せよ、あらゆる相違をより大きな全体に一体化せよ。
それが成長の法則である。相違の一体化は、生の永遠のプロセス、つまり創造的総合、創造という最高の行為」
そして、『本当の自由』を次のように解説しています。
「個人が自らの強み、潜在能力を発揮し、社会全体へその能力を結びつけることによって、はじめて個人の個性が発揮され、同時に個人的成長と全体の発展が可能になる。
同時に、『全体の中で個性を発揮すること』は、『個の中で全体を反映すること』。
個人の機能はお互いに関係づけられて統一的な全体を形成していくものであり、その関係の在り方は無限に存在する。この関係を通じて個人は自らの中に社会全体を体現していく。
自由の本質とは『関係の充実』。
私という存在は、二つの理由によって自由である。
(一)私が全体であるために全体によって支配されることはない
(二)私が他の人々をあるいは他の人々が私を統制せず、すべての人々が集合的アイディアと集合的意思を生み出すために混合するときにのみ、私たちは真の社会過程を有しているので、私は他の人々によって支配されない。
個人が自らの強み、潜在能力を発揮し、新たな集合的アイディア、集合的意思を創造するとき。
つまり、「新たな価値」を生み出すときに本当の自由となる。」
※フォレット (経営学史叢書 4)より抜粋、出版社:文眞堂
相手との間に生じた相違・すれ違いが、それぞれの強み、潜在能力を発揮させ、新しい可能性を創り出すのです。
人間関係に役立つコミュニケーションの基本テクニック

コミュニケーションの主人公は、自分ではなく「相手」です。
ここでは、話の聞き方、返し方の基本テクニックを紹介します。
傾聴の重要性
良好な人間関係を築くために、「傾聴」は重要なスキルです。
傾聴は、ただ相手の話を聞くことではなく、相手の言葉の正面にある意図や感情を深く理解しようとする積極的な行為です。
傾聴の本質
傾聴は、相手が自分の意見や感情を安心して表現できる環境をつくります。
そして、 相手の表面的な話を「聞く」だけではなく、「相手が本当は何を言いたいのか」「どんな感情を抱いているのか」に心を向けましょう。
このような共感する姿勢が、傾聴には求められます。
オウム返し
傾聴の一部には、相手が話した内容を確認する目的で、オウム返しすることも含まれます。
例えば、「○○さんが言ったことは、✕✕という意味ですか?」と問い返すことで、相手は自分が理解されていると感じ、より深く話すことができます。
感情の確認と共感
相手が不安、怒り、悲しみなどの負の感情にいる場合、その状態に共感を示すことで、より信頼関係が深まります。
「我以外皆我師也」起きている出来事が学びの機会

「我以外皆我師也」(われいがいみなわがしなり)という言葉は、思想家であり教育者でもあった吉川英治が語った有名な言葉です。
この言葉は、「自分以外」のすべてが師であること、誰からでも何かを学ぶ姿勢や、常に学ぶことを忘れない謙虚さを強調しています。
このように生きられれば人間関係も上手くいくことでしょう。
謙虚な学びの姿勢
「我以外皆我師也」として関わる姿勢は、他人を軽視せず、誰であっても自分にとっての教師になるという考えを示しています。
年齢や経験に沿って、周囲から学ぶことができるということを認識し、常に学び続ける姿勢を持つことが重要です。
また、この姿勢が、学びのプロセスが生涯続くものであることを示唆しています。
人は一度何かを学んだら終わりではなく、常に新しい知識や視点を得ることで、成長し続けることができるというメッセージです。
自己中心的な考えの否定
「我以外皆我師也」は、自己中心的な考え方や他人を見下す態度を否定しています。
謙虚さが人間関係を豊かにする基礎となります。
コミュニケーションは相手が主人公です。
どんなに真剣に関わっても、相手に受け取ってもらえなければコミュニケーションは失敗なのです。
逆境からも学べる
この考え方は、困難や失敗、逆境に対しても「学びの機会」として認識することができる力を与えます。
振り返ってみてください。私たちは、どんなときに成長してきたでしょうか?
試練やストレスを乗り越えることで、私たちは成長してきたのではありませんか?
もしそうであれば、人間関係で不一致が起きたときこそ、「相手を理解し尽くせない現実に向き合い続けること」で、一つの理解ができたときなのかもしれません。
まとめ

今回は、人間関係を円滑にするコミュニケーションについてお伝えしました。
職場の人間関係を良好にするためには、「相手を理解しようとする姿勢」と「相手を完全に理解できないという現実を受け入れる」ことの両方が大切です。
コミュニケーションは、単なる情報交換ではなく、お互いを理解し、信頼関係を築くための手段です。
傾聴や共感といったスキルを身につけ、相手との違いを学びの機会と捉えることで、より深い人間関係を築くことができるでしょう。