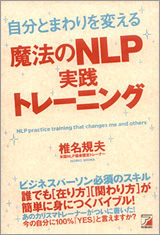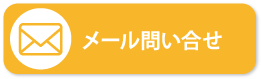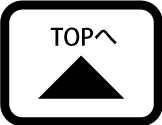何もないのにすべてがある場所
投稿日:2025年11月7日 / 最終更新日:2025年11月7日
目次 [閉じる]
満たされるとは
先生。「ここには何もないのに、すべてがありますね」。すると、「わかってもらえてありがとうございます」と言った。何もないことを、わかるって不思議なことだなぁと思いながら、なるほど、先生は意図してこの空間を作っていることに気づいた。
古臭い言葉だけれど、彼はカリスマ美容師。表参道でそう呼ばれていた。そんな彼と会うために、山を二つくらい超えて髪を切りに行く。以前、「先生、どうすればカットの技術で一流になれる人と、そうでない人がいるのか?」と尋ねたことがあった。すると、やさしい口調で「なんなんでしょうね。どんなに教えても、それを教えられないんですよね」。
それをセンスの違いで片付けてしまうのは、少し違うような気がした。技術は伝えられない。それは何なんだろう。
教えることができない
何の因果かは分からない。なぜか、面談を仕事とする人たちに、言葉を教える仕事をしている。個人面談、定期面談、査定、日々の業務で誰かと面談する。彼らは、対人支援者、人材育成担当者、リーダー、管理職、教師、メンター、コーチ、カウンセラー、セラピストたちであり、広く言えば人と接する仕事がすべて含まれるかもしれない。
営業マンや治療家、医師、看護師、福祉関係、教育関係、司法、産業……。
教える形式はいろいろ。研修、講座、個人セッション、グループセッション。グループセッションでは、毎回、筋書きのないドラマが始まる。そりゃそうだ。面談に協力してくれるクライアント役は毎回違うし、テーマも人それぞれ。
毎回、たった一度きりの本番。ワクワクする。失敗することも屡々(しばしば)。反面、その場の一言でクライアントを変容させる言葉を紡いできた。
クライアントが変容する瞬間に起きること。クライアントが語った言葉の奥にふれ、ガイドから紡がれた言葉の奇跡。それは一つの純粋経験。絶対矛盾的自己同一が起きた瞬間。
クライアントが苦悩してきた。何ものでもない空という混沌から生み出される言葉を、ガイド役がイデアの力を借りて、秩序となる言葉にして伝え返す。ガイドの力ではない。ロゴスとイデアの饗宴。言葉の芸術と言ってもいいと思う。そんな言葉が紡がれたときには、現場で拍手喝采が起こることもある。イデアとロゴスが喜んでいる。
一言でクライアントが変容する。初めてそんな経験をしたのは1998年。
その日だけで数名が生き方を変えた。それはまさに、より善く生きようとする者たちが、人生の新たな扉、道を開いた瞬間に立ち会ったようなものだ。
なぜわかるのか。当時から一緒に学んだ者たちが、10年後、20年後、その時の出来事からの人生の変化を教えてくれるからだ。もちろん、彼ら一人ひとりが真摯に選択した人生を歩んできたからだけれど。岐路を選択する力は、あの時の、あの一言から培われたものだろう。
一言で人が変容していく言葉を使えるようになりたい。そういう存在になりたい。そう決断するまで、時間はかからなかった。それから身につけるまでに10年が過ぎた。そして、そういう言葉の紡ぎ出し方を教える立場に立たされるようになった。自らではない。周りから言われて、自ずからそういう役割を与えられた。自然には逆らわない。
「どうすれば、あの言葉が出てくるんですか」
そんな質問には、先人に教わったことを、そのまま伝えるしかない。先人が一言でクライアントを変容させる。クライアントが変貌する瞬間を、感動とともに、ずっとずっと、四半世紀、見続けてきた。あんなふうな言葉を使えるようになりたい。絶対になってやる。そう決心した。その時と同じ気持ちになる者たちが、そういう講座の参加者たちにも生まれてくれる。ありがたいことだ。
さて、どうすれば魔法のような言葉が紡げるようになるのか。目の前の師に教えてもらうよりも、技術を盗むことを心がけて約10年。それでも、奇跡が起こる魔法の紡ぎ出し方が分からない。だから聞いた。どうしたらできるようになるのか。
「天から降ってくる」
最初にこの言葉を聞いた者は、おちょくられていると勘違いするだろう。だけれど、魔法のような言葉は、まさに天から降ってくるのだ。厳密にいえば、それは日常的に律動として起きている。しかし、それをわれわれは掴めない。いや、エゴが邪魔して、触れている、掴んでいることに気づけないのだ。
伝えられない
出し惜しみではない。気の利いた言葉を紡ぐ技術はシンプル。あまりにもシンプルすぎて、信じてもらえないのが実情だ。
その方法は、ガイドが心を空っぽにして、クライアントが一番最初に話す言葉から、背景にある存在を感じ取る。相手の最初の言葉が最大のヒントだ。
それを逃してしまうと、その後、数分は話を聞くだけの作業になる。最初に感じ取り、何かを掴めなければ、セッションが長引くだけになるのだ。最初に掴めば、あとはシンプル。感じ取った感覚をロゴスにしてイデア界に投げかける。そこで想起されたロゴスを、的確に言葉にすればいい。
シンプルすぎる。それを分かりやすく伝えても、グループセッションの参加者は「分かりました」と言う。せめて「感じました」と言ってくれたら、うれしい。なぜならば、テクニックは言葉で理解するものではなく、感じることが先で、頭で理解することはできないからだ。
真実は伝わらない
技術は教えることができない。美容師の先生が言ったことと同じだ。もしかすると、カットもそうなのか。目の前の頭の形をどうすべきかと空に問うのか。すると、イデアがイメージとして彼に返してくれるのかもしれない。
カリスマ美容師のカットは精緻だ。ハサミとクシで40分カットする。そんなに時間をかけなくてもと思うけれど、プロの眼差しに、何も言えなくなる。次回は、頭のてっぺんのボリューム感を出して、少し長めのデザインにするらしい。カット中に、イデアから新たなロゴスが降りてきてしまったのだろう。
謎の存在
最近、一緒に心理学を学んだ仲間と15年ぶりに出会った。不思議な税理士で、仕事に飽きてしまったのか、取手までやってきて芸大の関係者と農業をしている。それも、毎朝やっているそうだ。朝、体を動かすと自然と一緒にいる感覚を味わえるという。
そう。重要なのは感情じゃなくて感覚。感情は、それに流されたり、自分の中心から離れていってしまう心理機能。感覚は違う。本質につながることができる。彼は「本当の自分と触れているようだ」と言った。
デジタルクリエイターでもある彼。「どうやって、それをつくるのか?」と尋ねた。すると、イメージをしてから作り上げていくと言っていた。そのイメージはどこから生まれるのか。やはり、お客様との打ち合わせをした時の感覚から来るのではないかと思った。
クリエイター本人が作りたいものではなく、お客様が求めるものを感覚しないで、どうやってイメージできるのか。お客様の要望と彼の感覚の間には何があるのか。彼の感覚とイメージの間には何があるのか。イメージされたものと、マウスを動かす指先の間には何があるのか。そこには、何ものでもなかった混沌という空から、何かが紡ぎ出されて、芸術になっていくのではないか。
珈琲焙煎教室の準備
自宅でおいしいコーヒーを淹れたいというニーズを持つ方は多い。そして、自宅で焙煎したいというニーズの方も多い。妻の手伝いで、プロ並みに珈琲豆を焙煎している。プロ並みと言っても、1週間のうち休日の二日間をそれに専念する程度。3年近くも続ければ、そりゃ上手くなる。
近いうちに、珈琲豆の焙煎体験教室を開催することになった。そこで、プロ用の焙煎機では、参加者が自宅に帰ってからの自家焙煎の参考にはなるまいと思って、3万円程度で気軽に焙煎できるマシンを揃えた。マシンと言えるほどのものではない。
準備はしなくちゃね。ちゃんと煎れるのか。このマシンで、ちゃんと焼けるのだろうか。不安だらけのチャレンジ。1回目、やや焦げすぎて失敗。2回目、浅すぎて失敗。3回目、まぁまぁの出来。妻に試飲させて、お店でも試飲してもらうように提案。あえなく却下。不合格。
4回目。これまでの焙煎機での経験を捨てた。新しい小さな焙煎機が、珈琲生豆と奏でる音に耳を傾け、豆の変化を観察して、ゆっくり待った。慣れているマシンのようにはいかない。だけれど、焼き上がる頃に、珈琲豆が「そろそろです」「今です」と伝えてくる。その感覚を受け取り、イワタニのカセットコンロの火を止めた。
うまい。妻が、試飲で採用してくれた。これまでの思い込みは役立つ場合もあるけれど、成功を邪魔してしまうことだってあるんだ。何度も繰り返して経験してきたことだけれど、その時に悟ったことは、忘れてしまっているものなんだ。その瞬間瞬間にしか突破口がないんだな。そうだよな。今しか生きられないんだから。
変わらない人
地元の仲間から、今どんな仕事をしているのかと聞かれる。正直に、分かりやすく「管理職やセラピストが使う魔法の言葉を教えている」と伝える。見事に誰にも信じてもらえない。口の悪い友達からは「昔から口が上手くて詐欺師っぽかったから、似合っている」と言われる。最高の誉め言葉だ。強みを生かして生きている。
一度形成された印象、既成概念を変えるのは難しい。自ら変えようとしなければ、社会の変化にも、誰かが変わったことにさえ気づかない。だいたい、上手くいかないのは自分の外側の責任なのだから、仕方がない。
そんな折、古くからの友人が不倫を始めた。不倫相手にはお子様が二人。別居して暮らすご主人がいる。友人に「旦那にバレたら大事だから、いい加減にしとけば……」と伝えた。友は、旦那とは話し合いがついているという。
この不倫はめずらしい。ご主人公認の不倫は、初めての体験。実は、友人が口から出まかせを言っただけ。周りの者たちは、その二人が不倫していることを話のネタにして盛り上がっている。友人は、そんなことも知らずに、旦那にバレていないふりをしている。思い込みは困ったちゃんだ。
そのことを、他の友人と会った時に「あれでいいのか」と聞いてみた。すると、そいつは分かっていた。「何を言ってもダメなヤツに、何を言ってもしょうがないでしょう。うちの家内の友だちと、俺の友だちが不倫している。それを思うだけで、関わりたくない」。その通りだ。妙に納得した。それを判断したのは、感情ではなく感覚だ。
自ら変わろうとしない者。何かおかしな状況になってしまっている者。そこから脱しようと思わなければ、そのままなのだろうな。気づくことがなければ、ゆでガエルとなって、地獄のような体験になるまで、どうにかしようとはしないのかもしれない。不倫はよくないとの思い込みは大きなお世話のようだ。
その気づけない状態は、誰にでも起こっていることであり、他人事だなんて言えないことだ。不倫している彼は、快楽という感情の中にいる。恋をしている。温もりを求めている。そうでなければ、午前二時ごろにコインランドリーで一人、洗濯している様子などSNSに投稿しないだろう。誰に向けた投稿なのか。すぐわかる者には分かってしまう。
今の彼には、その彼女しか見えない。欲望というアリジゴクの中にいる。情の中にいれば、善悪を感じる感覚が鈍ってしまうのは、人間の性質なのだろう。
酒の飲みすぎも似ているような気がする。飲んでいる時は楽しいけれど、自分の身体を大切にしようとする感覚を見失っているのではないだろうか。感情を悪者にするわけではないけれど、自分を取り戻すには感覚が重要だ。それでは、どうすれば善く生きるための感覚を磨き上げることができるのか。どうすれば気づく主体となって生きることができるようになるのだろう。
情は強い
感情に振り回されながらの人生は、上手くいかなそうだとは気づける。信じることをやめない女性がいる。彼女が別れた旦那に車を貸したら、事故をされたらしい。その出来事のどこに不都合があるのか。元旦那が車の保険に加入していなかったので、持ち主の彼女に損害賠償請求が来たのだとか。そんなことが本当に起こるものなのか。真偽のほどは分からない。ただ、別れた元旦那に1年以上、車を貸しておくとは、どういう事情があったのだろうか。
直覚や直観で、貸した方がいいと思ったのか。そんなことがあるはずがない。「かわいそうだなぁ」「しょうがないなぁ」という感情が起きて、そうしてしまったのだろう。感情は悪者ではないけれど、感情は正しい判断を誤らせることがある。
車を貸してしまった彼女の話のオチ。「嫌な予感がしていたんだ」。
この予感は感情か。感覚か。感覚だろう。感覚は信じるべきではないか。
彼女が二度と元旦那に車を貸すことはないのであろうか。心配した。心配が感情だとすれば、またやっちゃうのかなと感覚したことなのか。
真実は一つ
15年ぶりに再会したデジタルクリエイターは、税理士という仕事を副業レベルにして、毎朝の畑仕事で自然と一つになる快感に酔い、芸術家としての新しい一歩を踏み出した。60歳を過ぎてのチャレンジは、勇気がいるものだろう。
バツ2。旦那がいる女性と不倫する友人も、人生最後の悲劇を迎えることになるだろう。なぜ、彼女のために手を引かないのか。なぜ、一人娘に誇れる背中を見せるために、美しく生きようとしないのか。孤独を解消させるための情愛は、まったくもって感覚を鈍らせる。周りは、とばっちりを被らないようにするしかない。
誰もが、普段からロゴスとイデアと仲良くしなくちゃね。
魔法の言葉と神様
美容室は、山奥のそば処にある。毎回、いろいろな蕎麦屋に行くのも、美容室へ行く楽しみの一つだ。すると、どのお店にも忙しく働いている店員がいる。余裕がなく、笑顔もなく、必死だ。
心の中でつぶやく。笑顔で仕事すれば……。心がここにないのがお客様にダダ漏れだよ……。お店に入った時からブスッとした顔をしてちゃ、おいしいおそばが台無しだぞ……。
そんな店員さんがいるお店でも、魔法の言葉をかける。そばの味が期待と違っても、言葉とともに生きていきたい。
店から出るとき、お会計で声をかける。「忙しい中、大変ですね。人手不足なんでしょう。ご自身のこと、大切になさってくださいね。お蕎麦、おいしかったです。ありがとうございました」。
この言葉は、人材育成担当やセラピストを教える立場の者だけが語るレベルではなく、誰でも語れる言葉だ。
なぜ、こんな言葉をわざわざ伝えるのか。神様に言われるんだ。「無条件に優しい言葉をかけてもらえないだろうか」。
神様は、いつも優しい。人間の心のモヤモヤを超えて、美しい言葉をかけることで、蕎麦屋で働く者と食事をした私たちを満足させてくれる。
怒りやねたみを感じた時、その感情をそのまま言葉にするのか。それとも、目の前にいる余裕のない者が一所懸命に働こうとしている感覚に気づき、ねぎらいの言葉をかけるのか。それは自分自身へかける言葉だ。
「ネガティブな感情を我慢してストレスがたまりませんか」「私の気持ちはどうなるのですか」と質問されることもある。ストレスなどたまらない。負の感情を表に出せばストレスが小さくなるのか。それは逆であろう。負の感情を相手にぶつけてしまった罪悪感で、余計にストレスが増すのではないか。
目の前の人を笑顔にする言葉を紡ぐ。その言葉は、ストレスという出来事さえ美しさに変える。誇りとなって、自分の人生を深く彩るようになるじゃないか。
なぜ、表参道で名を馳せていたカリスマ美容師が、山奥で一つのカットチェアのお店を開いたのか。それは、人ごみの都会を嫌ったのではないと思う。髪型で日常生活を豊かにする仕事をしているのだ。お客様の髪型に、魂の灯をともしている。都会で仕事をしていた時、そんな感覚を味わったことだろう。そんな仕事をもっと丁寧にしたくて、たった一人で働く美容室を始めたのだろう。
なぜ、一言で相手が変容する魔法のような言葉を紡げるのか。
なぜ、教えても真似できないハサミとクシで髪の芸術が完成するのか。
なぜ、税理士という安定した仕事を手放し、自然と芸術の中に飛び込んできたのか。
神様にふれられるんだ。「こっち、こっち、こっちの水はあーまいぞ」。
けっして甘くはないんだけれどね。
美しく生きられる。