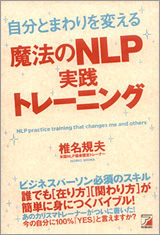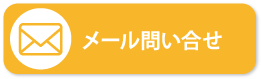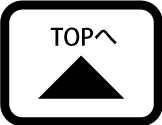【完全版】ストレス解消法・対処法ガイド|なぜ80年前に「ストレス」は存在しなかったのか?
投稿日:2025年10月9日 / 最終更新日:2025年10月9日

ストレスを解消したいと願う人は多く、イライラや疲労感など、その影響は計り知れません。
この記事では、ストレスをストレスと感じない人たちが持つ、ストレスをポジティブなエネルギーに変える考え方と、その実践的な方法を解説します。
ストレスで悩む人、ストレスを感じない人

現代人は日々、さまざまなストレスにさらされています。
ストレスを感じたとき、早く解消したいと願う人は多いでしょう。
ストレスをストレスだと感じない人
ご存じのように、ストレスは感情や行動に大きく影響します。
- イライラする
- 気を使いすぎて疲れる
- 自身が持てない
- 後悔することが多い
- 上司や同僚と合わない
- 小さなことにすぐ腹が立つ
- 本音が言えない
その一方で、ストレスをストレスだと感じない人もいます。
「そんなの嘘だ」「信じられない」と思う方もいるかもしれません。
かつて私もそうでした。そんなとき、ストレスを避けるのではなく、楽しむ方法を教えてもらったのです。
それ以来、私はストレスをストレスだと感じなくなりました。
深呼吸や瞑想だけでは解消できない理由
たとえストレスを感じたとしても、私はすぐに解消できるようになりました。
これは、深呼吸やマインドフルネス瞑想のような一時的な方法ではありません。
なぜなら、瞑想で得られるのは一時的な安定した心理状態であって、「生きる上で本当に必要な真実を知ること」ではないからです。
日々の些細な出来事から、人生における大きな試練まで、ストレスの原因となるものは誰にでもあります。
それなのに、それをストレスだと感じる人と、そうでない人たちは、一体何が違うのでしょうか。
ストレスの誕生とその正体

私たちは日常的に「ストレス」という言葉を使いますが、その生みの親が誰か、そしてその理論がどのような背景で生まれたのか、ご存じでしょうか?
ストレス研究の父、ハンス・セリエ
1930年代、ハンス・セリエというオーストリア人科学者は、動物がどんな種類の刺激(寒さ、暑さ、ケガなど)を受けても、身体が常に同じような反応を示すことに気づきました。
彼はこれを「汎適応症候群(General Adaptation Syndrome)」と名付け、この外部刺激に対する身体の反応が、私たちが今「ストレス」と呼ぶ概念の始まりとなったのです。
セリエは人間への研究・検証をほとんど行わず、ストレスを「病気の原因となるもの」と位置づけました。
この理論は世界中に広まりましたが、彼にはあまり知られていない衝撃的な事実があります。
煙草産業に利用された暗い歴史
セリエのキャリアには、取り返しのつかない負の側面があります。
1960年代以降、彼の研究資金の一部が、なんと煙草会社から提供されていたことが判明したのです。
セリエは「喫煙はストレスを和らげる」と発言するようになり、結果的に煙草産業の広告塔として批判されました。
これは、科学が産業に利用された痛ましい事例として、今もなお語り継がれています。
ストレスは本当に悪者?晩年のセリエがたどり着いた答え
セリエは晩年、ストレスに対する自身の考えを大きく修正しました。
彼はストレスを単なる害悪とは見なさず、良いストレス(ユーストレス)と悪いストレス(ディストレス)に分類しました。
- ユーストレス:成長や挑戦の原動力となるポジティブなストレス
- ディストレス:心身を蝕み、健康を害するネガティブなストレス
1974年の著書『Stress without Distress』(苦悩なきストレス)で、彼はこの考えを広め、「ストレスそのものが問題なのではなく、それをどう扱うかが重要だ」と主張しました。
この考え方は、今日のポジティブ心理学やセルフケアにつながる重要な転換点となりました。
しかし、ストレスが悪であるという概念を完全に払拭することは、未だできていないのが現実です。
ストレスがなかった時代?江戸時代の知恵

「ストレス」という言葉が日本に伝わったのは、戦後のことです。
では、それより前の江戸時代の人々は、心の不調とは無縁だったのでしょうか?
どの時代でも心身の悩みや不調は起きる
現代のような「ストレス」という言葉はなかったものの、江戸時代の人々が心身の悩みや不調を抱えていたことに変わりはありません。
彼らは、これを「気が病む」「気がふさぐ」「心痛」「憂鬱」「気疲れ」「心労」などと呼びました。
しかし、一部の聖人と呼ばれる人々は、そうした苦痛を「日々新た(ひびあらた)」と捉え、独自の知恵で乗り越えていたのです。
「日々新た」とは
「日々新た」とは、ただ毎日を新鮮な気持ちで迎えるだけではありません。
それは、日々の些細な出来事一つひとつに驚き、感動し、新しい発見として生きることです。
その積み重ねこそが、私たちを縛りつける心の鎖、つまりストレスを乗り越える力になっていくのです。
この考え方は、現代にも通じるのではないでしょうか?
- 仕事でのトラブル
- パソコンの動作停止
- 感染症背筋が凍るような凶悪事件
- 突然の天候不良
- パートナーの勘違いによる怒り
- 上司からの心ない叱責
日々、自分の常識を超える驚きの連続ではないですか?
現代におけるストレス解消法・対処法

現代のストレス解消法・対処法は、単にストレスを避けることではなく、それを人生の成長機会として捉えることにあります。
「日々新た」の精神でストレスをリセットする
「日々新た」の考え方は、普遍を生きるための智恵です。
これを実践することで、私たちはネガティブな感情や思考をリセットできます。
視点の転換
ストレスを感じるような出来事も、「常識を覆す面白いハプニング」や「宇宙レベルのジョーク」として捉え直すことで、心が軽くなります。
考え抜いた計画がうまくいかないとき、それを最悪な出来事ではなく、「予期せぬ改善点が待っている」と捉え直すのです。
この考え方は、ストレスの根本原因を解決するものではありませんが、心の回復力を高め、ネガティブな感情の蓄積を防ぎます。
ストレスは「大切なことに触れられた」ときにしか生まれない
スタンフォード大学の心理学者ケリー・マクゴニガルは、「ストレスは、大切にしていることに触れられなければ起きない」と主張しています。
- 仕事でプレッシャーを感じるのは、その仕事に価値を感じているから
- 人間関係で悩むのは、相手との関係を大切にしているから
- 将来への不安を感じるのは、自分の未来を真剣に考えているから
この考え方を取り入れると、ストレスは単なる「邪魔なもの」ではなく、自分にとって何が重要かを教えてくれる羅針盤になります。
ストレスを成長の機会に変える
ストレスには、心身を蝕む「ディストレス」という悪い面がある一方で、人を成長させる「ユーストレス」という良い面もあります。
ストレスを乗り越える過程で、私たちは新たな能力や知恵を身につけます。
難しい問題に直面した人は創造的な解決策を導き出す力が養われ、プレッシャーの中で成果を出した人は「レジリエンス(精神的回復力)」が高まります。
これは、私たちがストレスにどう向き合うかによって決まります。
ストレスを避けたり、無視したりするのではなく、その原因を深く掘り下げ、そこから何を学べるかを考えることで、ストレスは成長のための「試練」へと変わるのです。